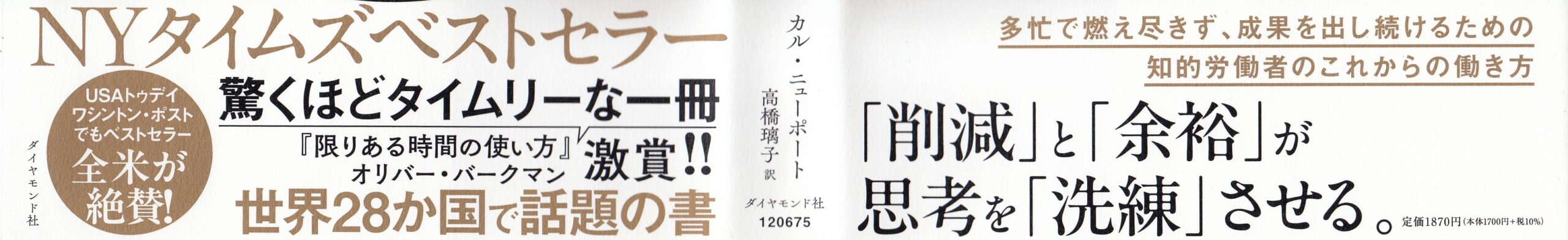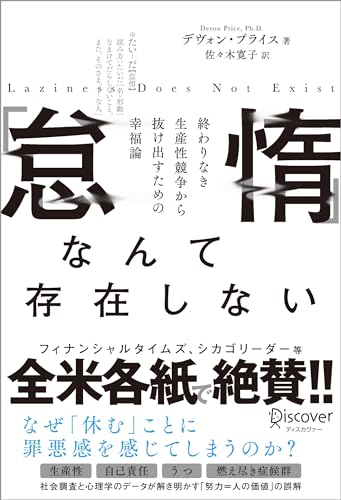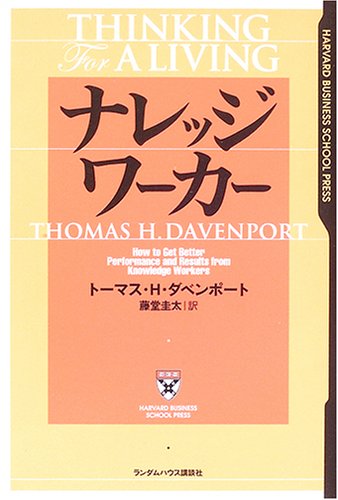忙しければ「生産性」が高い訳ではない
知的労働の問題は生産性そのものにあるのではなく、生産性の誤った定義にあるのではないか。過重労働は、生産性を「忙しさ」と同一視する風潮に由来する。しかし、満杯のタスクリストを抱えて活発に動き回るよりも、ゆっくりと、静かに動く方が生産性が高い可能性もある。
現代の過重労働に代わる新たな仕事観は、忙しさを否定する「スローワーキング」だ。これは、持続可能かつ有意義なやり方で知的労働に取り組むための仕事哲学であり、以下の3つの原則に基づく。
- 削減:やるべきことを減らす
- 余裕:心地よいペースで働く
- 洗練:クオリティにこだわり抜く
過剰な労働は決して名誉ではなく、成果を妨げる障壁である。仕事はもっと変化に富んだ人間的なペースで進めるもので、集中的に働く時期もあれば、ゆっくり休む時期もあっていい。
第1原則:やるべきことを減らす
やるべきことを大幅に減らし、すべて終えてもたっぷり時間があるくらいにしておくこと。少数の重要な仕事に力を注ぎ、大きく前進すること。
知的労働者が何か仕事を引き受ける時には、必ず「間接コスト」がかかってくる。間接コストとは、本来の作業を進めるために必要な周辺作業のことだ。例えば、情報をすり合わせるためのメールのやり取り、同じ仕事に関わっている人達とのミーティング。仕事量が増えてくると、間接コストが臨界点を超える。するとタスクを管理するための作業が1日のスケジュールの大半を占めるようになり、既存のタスクを終わらせるだけの時間が取れなくなる。
引き受ける仕事を減らした方が、アウトプットは明らかに増える。本来の仕事に使える時間が増え、さらに仕事をする時間の質も高まる。急いでいない時の方が、脳はうまく機能する。少ないタスクに集中力を注ぎ、1つの仕事を完了してから次の仕事に取り掛かる方が、はるかに優れた結果につながる。
仕事を減らすための方法は次の通り。
- 大きな仕事を制限する
仕事を規模別に「ミッション」「プロジェクト」「ゴール」の3つに分類し、ミッションは2、3個に絞り、プロジェクトの数を減らし、ゴールは1日1つに制限する。 - 小さな仕事を手なずける
定期的に発生するタスクはいつも同じ曜日と時間、場所、儀式で実行するように自動運転モードにする。 - 仕事はプル方式で取りにいく
各工程に空きができたタイミングで新しい仕事を取りにいく。
第2原則:心地よいペースで働く
重要な仕事は急がない。自然で無理のないペースを心がけること。遊びと変化を取り入れて、最高の成果につながる環境を作り出すこと。
スローワーキングは、無意味な多忙さを決して評価しない。常に追い詰められているなら、何かが間違っていると考える。一定の強度で休みなく働くのは人工的で、持続可能性のない働き方だ。もっと自然で、遅く、変化に富んだ仕事のペースこそが、長期的には真の生産性を育んでくれる。
人間らしいペースを取り戻す方法は次の通り。
- 時間はかかるものと考える
長期計画を決め、仕事に「これくらいかかる」という見積もりを2倍にする - 季節の変化を取り入れる
オフシーズンや短い期間などで仕事に強度の変化をつける - 芸術家の創作環境に学ぶ
仕事をする場所や雰囲気を選ぶ
第3原則:クオリティにこだわり抜く
仕事の品質を徹底的に追求する。短期的にはチャンスを逃すことになったとしても、その成果は長期的に仕事の自由度を大きく広げてくれる。
クオリティの追求は多くの場合、仕事のペースを落とすことに直結している。質を高めるために必要な集中は、多忙さと両立しないからだ。高品質な仕事には時間がかかる。しかし高品質な仕事を一旦達成すれば、仕事の主導権を握り、慌ただしいペースからさらに距離を置くことが可能になる。
仕事の削減と余裕の原則は、クオリティへのこだわりという要素がなければ、仕事との関わりを無味乾燥なものにしてしまう。クオリティへのこだわりによって、スローワーキングは単に忙しさを切り抜けるための戦略から、本当に有意義な人生を駆動するエンジンへと変容する。
クオリティを上げるための方法は次の通り。
- 誰にも負けないセンスを磨く
自分の専門分野だけでなく、他の分野の素晴らしさにも目をむけたり、同じ志を持つ仲間とつながる。 - 自分を信じて賭けてみる
少なくないリスクをとって自分自身に賭ける行為は、仕事を新たなレベルに引き上げるための戦略になる。