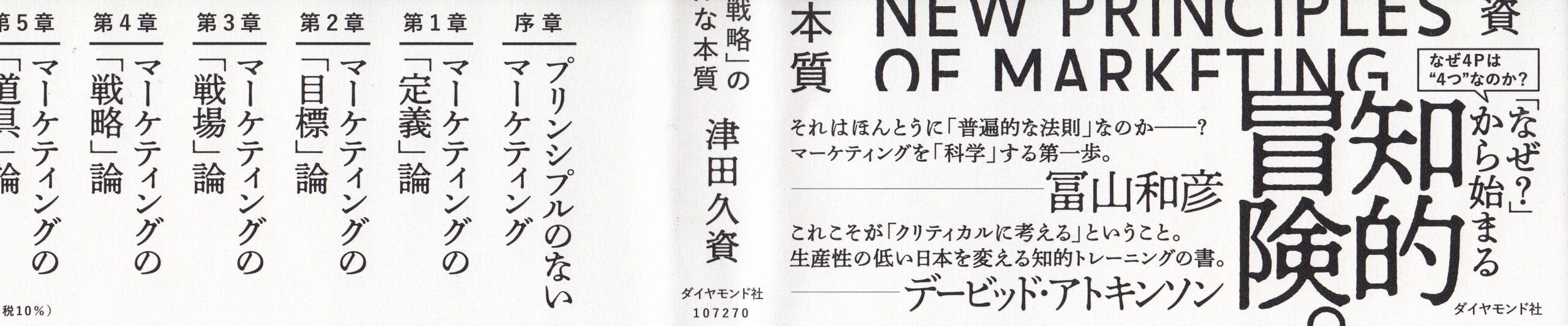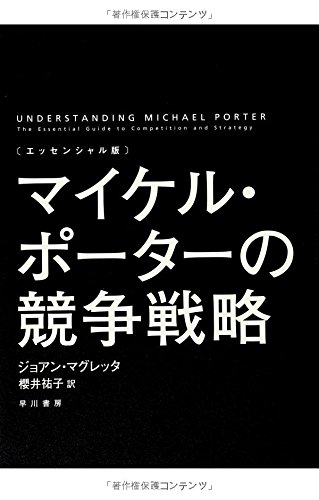マーケティングの目的論
マーケティングとは「一定費用の下で、適切な買い手群にとってよりコストパフォーマンスの高い商品を生み出し、その存在を認知させ、その内容を理解させ、これを送り届けることによって、粗利を最大化する総合活動」である。
一定費用の下で粗利を最大化しようとする時、カギになるのが「コストパフォーマンス(CP)」である。人が何かを買う時の判断軸こそがCPである。「負担するコストに対してどれくらい大きなパフォーマンスを得られるか」という観点なしには、人が何かを買うという行為は説明できない。
このパフォーマンスとは、その商品が持つ「属性(Attribute/Property)」によって生み出される「効能の価値」の総量であり、買い手がその価値に対して支払ってもいい「金額」として表される。パフォーマンスは、3つの要素によって決定される。
- 機能性パフォーマンス
- 情緒性パフォーマンス
- 効能を享受するまでにかかる時間の短さ
価値の高い商品をつくろうとする時、私たちはよく1つの機能的な価値の軸(Attribute)だけにとらわれてしまいがちである。もう1つ陥りがちなのは、機能性パフォーマンスばかり追い求めてしまい、その商品が持っている情緒性パフォーマンスを軽視してしまう失敗である。
商品が同じであっても、買い手が異なればその商品のパフォーマンスも違ってくる。優れたマーケターは、買い手が求めている属性をうまく分解したり翻訳する。
マーケティングの戦場論
よりCPが高い商品を生み出すだけでは、マーケティングは成功しない。商品を売る時には、ライバルが存在するからである。この戦場において「最高」のポジションをとるには、2通りの方法がある。
- 戦場で最もCPが高い商品を生み出す
- 競合がいない場に商品を投げ込む
1人1人の頭の中には「それぞれの戦場」が存在する。そして、戦場が変われば、商品のCPも変わる。一見すると、同じ戦場にありそうな商品同士でも、実は別々の戦場に属していて、競合になり得ないケースもある。このすれ違いの背景には、次の3つの要因がある。
- 求めるパフォーマンスが質的に違う
- 求めるパフォーマンスが量的に違う
- コストがあまりにも違う
マーケティングの世界では、競争の存在しない世界「ブルーオーシャン」がしばしば称揚される。「場に1つだけの商品が存在する状況」が生まれるには、買い手のニーズのあり方に応じて、それぞれ3つのパターンがある。
- ニーズはあったが、それを満たす商品が存在しなかった時(顕在的)
- 潜在的だったニーズを、売り手が商品によって顕在化させた時(潜在的→顕在的)
- 何もないところから売り手が新しいニーズを生み出した時(無→顕在的)
全く新たな軸の属性を持った商品を投げ込むと、買い手が潜在的に持っていたニーズが顕在化されることがある。このような時、「ブルーオーシャン」と呼べれるような競争が起こらないまま、購買の意思決定がなされる。
このブルーオーシャンを切り拓くための切り札がバリューイノベーションである。これを生み出す戦略立案のための要諦は、次の3つに要約される。
- 減らす
商品の価値が損なわれない範囲内で、自業界における一般的な価値属性(Property)の量を削る。それによってコストを削減して、商品のCPを高める - 取り除く
買い手にとって不必要な価値属性の軸(Attribute)そのものを切り捨てる - 付け加える
買い手が価値を感じる軸を新たに増やす
この中でも最も大事なのは3である。競争のない場を確実につくるためには、これまでにない新たな価値軸を付加しなければならない。
他方で、「新しい価値軸の付加」は必ずしも「新規買い手の獲得」につながるわけではない。既存の買い手の奪い合いにおいても、これまでにない価値属性を付け加える行為は有効である。「新規買い手の獲得」はあくまでも偶然の副産物でしかない。それゆえマーケターは、いきなり「新規買い手の獲得」を目指すのではなく、既存の買い手の中に隠されている潜在ニーズを拾い上げて、新しい価値軸を生み出すことに注力すべきである。
マーケティングの戦略論
買い手本人も気づいていない潜在ニーズを、赤の他人であるマーケターが発見することは可能なのか。買い手の潜在ニーズをつかむ方法は次の2つ。
①考える:自分の「内」にある情報を引き出す
自分自身の中にある「内なる買い手」に目を向けて、そこから潜在ニーズを汲み上げる。
②学ぶ:自分の「外」にある情報を取り入れる
別の空間・時間・カテゴリーにおいて顕在化されているニーズの知識を得て、それを目の前の買い手に応用する。
マーケティングはどこまでも「買い手としての自分を掘る作業」と切っても切れない関係にある。「自分だったらどういうものが欲しいか」という問いと不可分である。これには決まった「正解」はない。その意味で、マーケティングはどこまでも「アート」でもある。