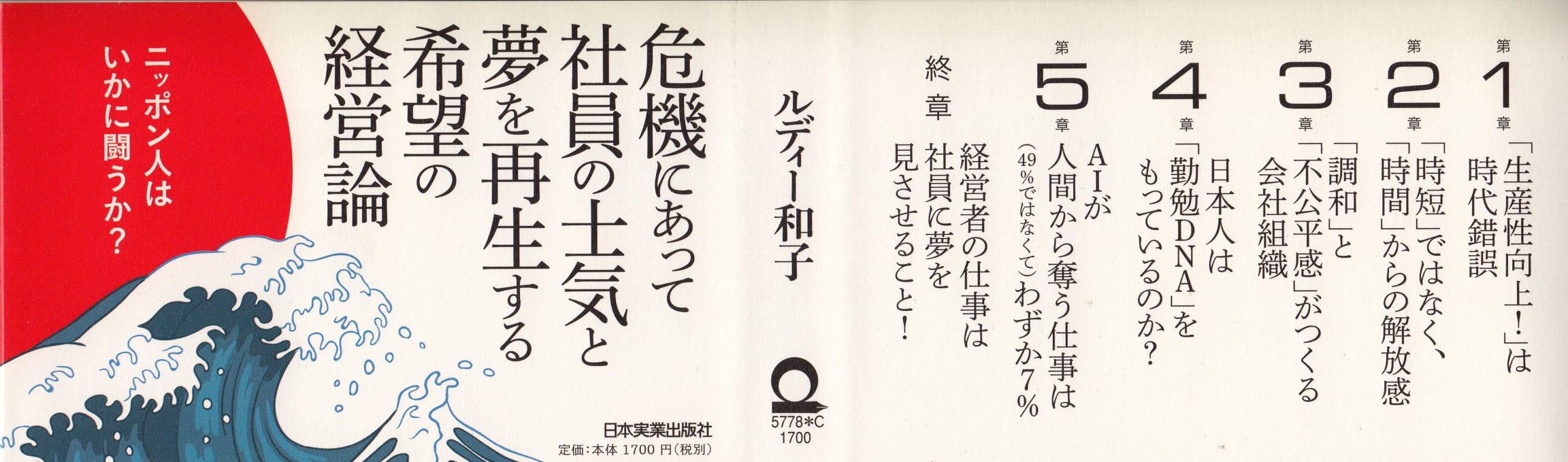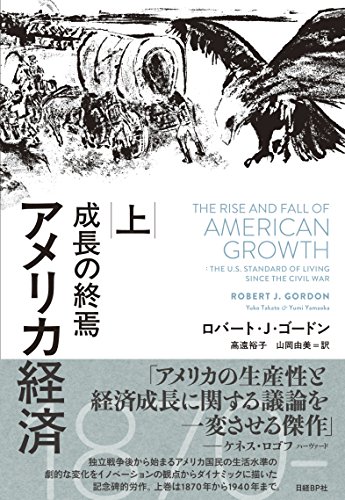日本はなぜ労働生産性が低いのか
労働生産性が低いことについて、「勤勉性」を関連づける意見をよく耳にする。だが、労働者の勤勉性に生産性の低い要因を見つけようとするから、勤務時間を減らせば生産性は上がるはずという短絡的な考え方になる。だから、「残業を減らして、同じ内容の仕事をしろってことか」という不満が従業員から出てくる。
生産性は、どの産業が国の中核になっているかによっても異なる。日本では、サービス産業がGDPの7割を占めるが、その内訳は、生産性の低い卸売・小売業や宿泊・飲食といったサービス業の割合が多い。日本の生産性を上げるために、生産性の高い成長産業に労働を移動すればよいという主張がある。しかし、世界の大手企業の多くがそれまでの中核産業を捨て、ICT産業や金融サービス業といった生産性の高い産業へと選択と集中を進めており、そういった市場での競争は激しく、グローバル競争では勝てないだろう。
それに、多種多様な商品が市場にあふれ供給過多になっている今、自分は豊かな生活をしていると消費者に実感させてくれるのはサービス業だ。GDPの成長を願うのは、国が金持ちになってもらいたいわけではなく、国民が健康や幸福を享受できる国にしたいからだ。生産性が高い産業に労働力を移行させればよいなどというのは、単なる机上の空論だ。
日本のサービス業やオフィスワークの生産性は、ITを導入すれば一定程度上がる。しかし、日本企業はIT化に投資をする代わりに、コスト安の非正規社員の雇用を増やすことで、また、正規社員にルーティンワークをさせることで、バブル崩壊後の経済停滞を乗り切ろうとした。
その結果、過去20年間で、日本の賃金は9%減少している。先進国で唯一のマイナス国だ。同時期に、英国は87%、米国は76%、フランスは66%、ドイツは55%も上昇している。賃金が上がっていない一方で、物価も上がっていないのでバランスは取れていると思うかもしれないが、20年近くも賃金が上がらないのでは、元気もやる気も起こらないだろう。どの調査会社が調べても、日本の従業員のエンゲージメント率は国際的に見ても低い。
GDPの成長を追いかけるための生産性向上はやめるべき
GDPが高いことはよいことだという観点から、持続的な経済成長は最重要目標であると考えられてきた。しかし、それに対して異議を唱える経済学者も登場してきている。GDPを絶対視することへの違和感が生まれてきた原因の1つは、GDPの成長が国民の暮らしと直結しなくなったことだろう。米国においては、2000年から1人当たりのGDP数値は上昇しているが、世帯当たり所得の中央値は減少している。GDPが成長したとしても、国民全体がその恩恵を受けない理由の1つは、格差の問題だ。
経済が成長しても、今の社会・経済システムでは、その結果を享受するのは一部の国民であることが、どの先進国においても明らかになっている。「富める者が富めば、貧しい者にも自然に富がしたたり落ちる」とする経済理論は、その正しさが実証されていない。
そして、OECDやヨーロッパの指導者たちは、現在のGDPは21世紀の社会の「ウェルビーイング(健康で幸福な状態)」を体現していないし、GDPの数値を使うことによって、経済成長のみを追求する政策に偏ってしまっていることを憂慮すべきことだとしている。今のGDPは、モノの生産量の指標を表しているだけで、人々の健康で幸福な状態の指標にならない。
政府や経済界が生産性向上を必死になって訴えるのは、結局はGDPの成長を維持したいからだ。しかし、そういった状況において、従業員に対して「生産性が低い」とか「生産性向上!」と言うのはやめるべきだ。今、必要なのは、数値で労働を考えるのではなく、質や内容で労働を判断することだ。