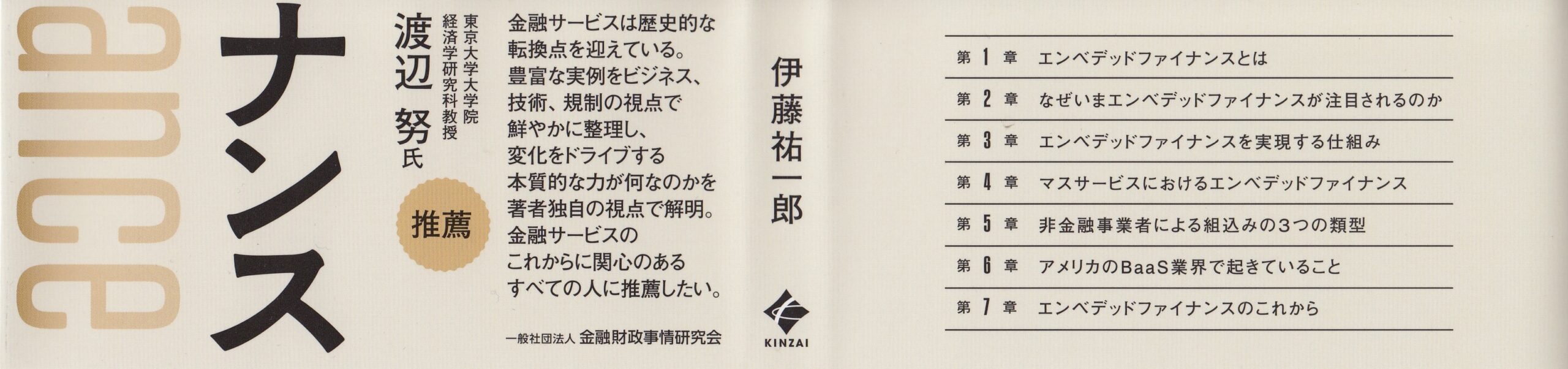エンベデッドファイナンスとは
近年の技術革新により、APIを通じて、金融機関が提供してきた機能や商品を第三者が提供できるようになってきた。これにより、利用者は金融機関の支店やウェブサイトを訪れることなく簡単に金融サービスを利用できるようになり、顧客体験が飛躍的に改善されただけでなく、以下のような多様な新しい金融サービスが登場し始めている。
- Appleがゴールドマン・サックスと提携して開始した預金サービス
- メルカリの決済サービス、少額融資サービス、アプリ完結型クレジットカード
- JR東日本のネット銀行サービス
- ヤフーのシナリオ保険
- Paypayの加盟店向け融資サービス
- レストラン予約アプリOMAKASEのキャンセル保険
こうした一般的なサービスの中で金融サービスも提供することを「エンベデッドファイナンス(組込型金融)」と呼び、近年、大きな注目を集めている。エンベデッドファイナンスの市場規模は、2024年時点で決済領域を中心に920億ドルに達しており、2028年には2280億ドルに拡大すると予測されている。
エンベデッドファイナンスの実現には、3つの不可欠な役割が存在する。
①ブランド
顧客との直接的な接点を持ち、アプリやウェブサービスを通じて包括的な顧客体験を設定・提供する。この役割の重要性は、金融機能を既存のサービスや製品にシームレスに統合することにある。単なる機能の統合だけでなく、顧客との信頼関係を構築し、ブランド価値を高めることで、従来の金融機関では実現が難しかった新たな顧客層の開拓や、革新的なサービスの展開を可能にしている。
②イネイブラー
ブランドとライセンスホルダーをつなぐ中間役を果たす。APIプラットフォームを通じて複数の金融機能をサービスとして提供することで、ブランドが独自のシステム開発やライセンス登録等の負担なく金融サービスを展開できるようサポートする。
③ライセンスホルダー
法的に必要な金融ライセンスを保有し、実際の金融商品やサービスを組成する役割を担う。イネイブラーを介してブランドと連携するが、法的にはあくまでもライセンスホルダーのサービスをブランドが提供する形式をとる。
これら3つの役割が相互に補完し合うことで、エンベデッドファイナンスは従来の金融サービスの枠を超えた、利用者中心のサービスを生み出している。
金融サービスの変化
金融サービス業界は、過去20年間で劇的な変革を遂げた。2000年代の「金融のオンライン化」は、運用コストの低減と大幅な手数料引き下げを実現し、2010年代の「金融のモバイル化」は、アンバンドル化を通じて複雑だった金融サービスの利便性を飛躍的に向上させた。これらの変革期において、企業は「他社よりも圧倒的に安い」「明らかに使いやすい」といった明確な差別化戦略を比較的容易に展開できた。
しかし、この20年間の進化を経て、金融サービスの差別化は次第に困難になっていった。その主な要因は2つある。
- 手数料引き下げの余地がほぼ消失した
- アジャイル開発の台頭により、類似の機能をすぐに実装することが可能になり、機能による差別化が困難になった
その結果、2010年代後半には顧客獲得単価が高騰し、多くの金融機関が持続可能な成長戦略の再考を迫られることになった。この課題を解決するアプローチとして浮上したのが、既に顧客を持っているプレイヤーが金融サービスも提供したら良いのではないかというアイデアだった。自社の販売チャネルの集客にコストがかかるのであれば、逆に既に顧客がいるところに金融機能を置いておくという発想だ。こうしてエンベデッドファイナンスに注目が集まるようになっていった。
エンベデッドファイナンスの波は、従来の非金融事業者だけでなく、金融の「モバイル化」や「アンバンドリング」を通じて台頭したフィンテック企業にも及んでいる。これらの企業は、当初提供していなかった金融機能も自社サービスに組み込むことで、総合的な金融サービスプロバイダーを目指し始めている。このようなアンバンドリングした業界が再びバンドルされていくトレンドを「リバンドリング」と呼ぶ。
リバンドリングの時代においては、クロスセルによるARPUの向上と同時に、ユーザーのリテンションが非常に重要になってくる。既存サービスのデータから得られるインサイトをもとに「これがあるからサービスを解約しづらい」と思ってもらえる機能やサービスをバンドルしていくことが1つの成功パターンになっていくだろう。