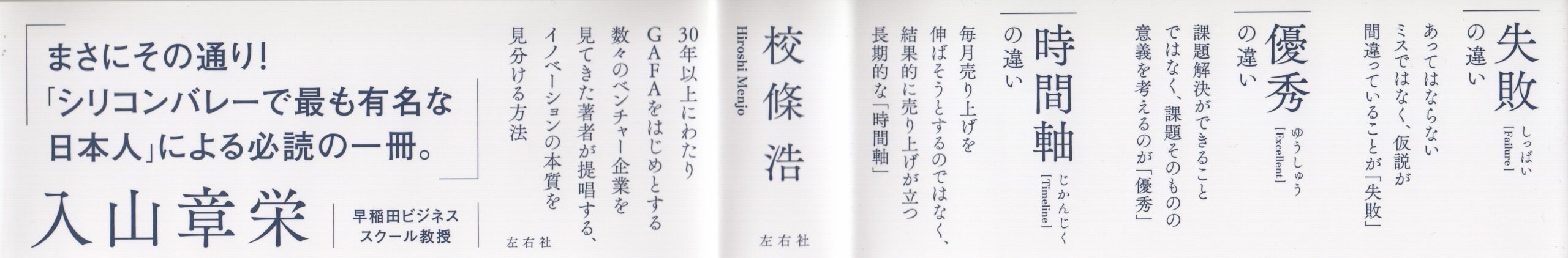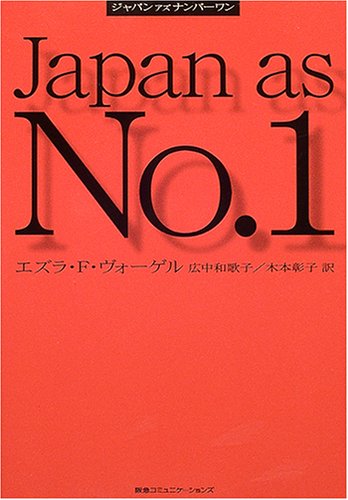日本企業が抱えるイノベーターのジレンマ
戦後の日本産業の興隆には「製品・サービスに関わる人たち全員が団結して、一生懸命真面目に取り組む」という大きく共通する1つの流儀があった。この流儀を実行しようとすると、「計画通り」に「みんなが同じ方向」を向いて、「オペレーション」を真面目に実行し、細部に至るまで分析して「地道に改善」に努めるということになる。これは戦後の復興後に驚異的な成長を遂げる強みになったが、「失われた30年」においては、企業変革や事業転換を妨げるイノベーターのジレンマに陥る原因となった。
デジタル誕生と以後では「全てがつながった」ことが一番大きな変化である。これまでは、産業ごとでばらばらに製品を作って売っていた。それがデジタル化によって、作った製品が他の製品とソフトウェアや通信技術でつながり、この「つながり」に新たなビジネスチャンスが生まれるようになった。
ビジネス的にも、トライ・アンド・エラーがしやすくなり、挑戦するにも失敗するにもコストが低くなった。また、デジタルで人々がつながっているので、製品・サービスに対するお客さんの反応も、リアルタイムに吸い上げることができる。このようにビジネスで上手くいくやり方自体も、根本から変わった。
「あらゆるサービスをつなげる」「小さな挑戦を繰り返す」「デジタルで意見を吸い上げる」などの新しいやり方には、日本産業がこれまでやってきた流儀が足枷となり、なかなか踏み切れないジレンマがある。
帰納法と演繹法
こうしたジレンマに対応できない根本的な原因は、「帰納」と「演繹」という1つの理論で説明がつく。
①帰納法
帰納法は、個別の出来事を集め、そこから共通点を見出す形で一般的な法則や規則性を見出す。つまり、帰納法では既に分かっていることや起こっていることが思考のベースとなる。
②演繹法
既に一般的に知られている理論や法則、前提から仮説を検証し、結論を導き出す。演繹法では大前提に揺るぎない一般論を用いることが重要になる。
帰納法が個別事例から一般原則を導き出すのに対して、演繹法は一般原則や理論から個別の結論を出す。つまり、帰納法が抽象度を上げていく流れなのに対して、演繹法は抽象度を下げていく試みである。
日本が大きなジレンマに陥った根本の原因は、戦後の経済成長期に根付いてきた考え方のベースが「帰納思考」である一方、現在の変化の時代に世界の経済発展のベースとなっているのが「演繹思考」であることにある。両者では最初からアプローチが全く異なる。帰納思考では、過去の成功例を前例として調べ上げ、その集大成として事業案をまとめていく。一方、演繹思考では、まずコンセプトを出発点として仮説を生むことから入る。
しかし、演繹思考を苦手とする日本人が多い。それは「過去の事例をお手本にして良いところを取り入れ、さらに改善する」という帰納思考がしっかり身についているからである。帰納思考では、既存の事業の延長線上で良いか悪いかを判断するので、新しいことがなかなかスタートできない。帰納思考も演繹思考もそれぞれ、利点と欠点がある。大事なのは、その違いを知り、意識することである。
演繹思考の組織をつくる
日本企業で演繹思考の経営を上手く進めるには、「帰納思考による企業運営の利点と実績を認めながら、演繹思考の取り組みをする」態度が大切である。そして、帰納思考の既存組織とは分けて、演繹思考で経営される別の箱を作ることが有効である。
①経営トップの意識を変える
経営トップは帰納思考がすべてではなく、他の思考体系の世界があるようだ、と思えることが演繹思考の取り組みの第一歩となる。帰納思考と演繹思考というお互いに180度考え方の違う取り組みを両方進めることができるのは、誰の忖度もする必要がない経営トップにしかできない。
②両利きの個人を見つける、育てる
既存組織とうまく関係が持てるような帰納思考の能力があり、かつ演繹思考で動く箱をつくる「両利き」の人材を見つけることが必要である。例えば、既存組織での仕事が目立っていて、どんな上司にでも反論したり、逆提案をしたりする尖った人材が適任である可能性が高い。
③演繹思考の箱をつくる
演繹思考で新規事業創造を進める箱は、試行錯誤を繰り返すことを予想しているので、小さく始める。帰納思考の価値観で運営して、リスク回避のための議論に時間を割くことを避ける。
④未来へ向けて、帰納組織を変革する
帰納組織に対して演繹思考を移植していく。演繹組織と帰納組織の人事は水と油のような違いがある中で、演繹組織の人事システムをどう運営するかは、現時点では明確な答えはない。
⑤箱の成果を検証し、古くなった帰納組織を徐々に吸収していく
演繹思考の組織でも動けるようなオープンマインドを持った人材が帰納思考の既存事業から出てくれば、企業の成長は続く。