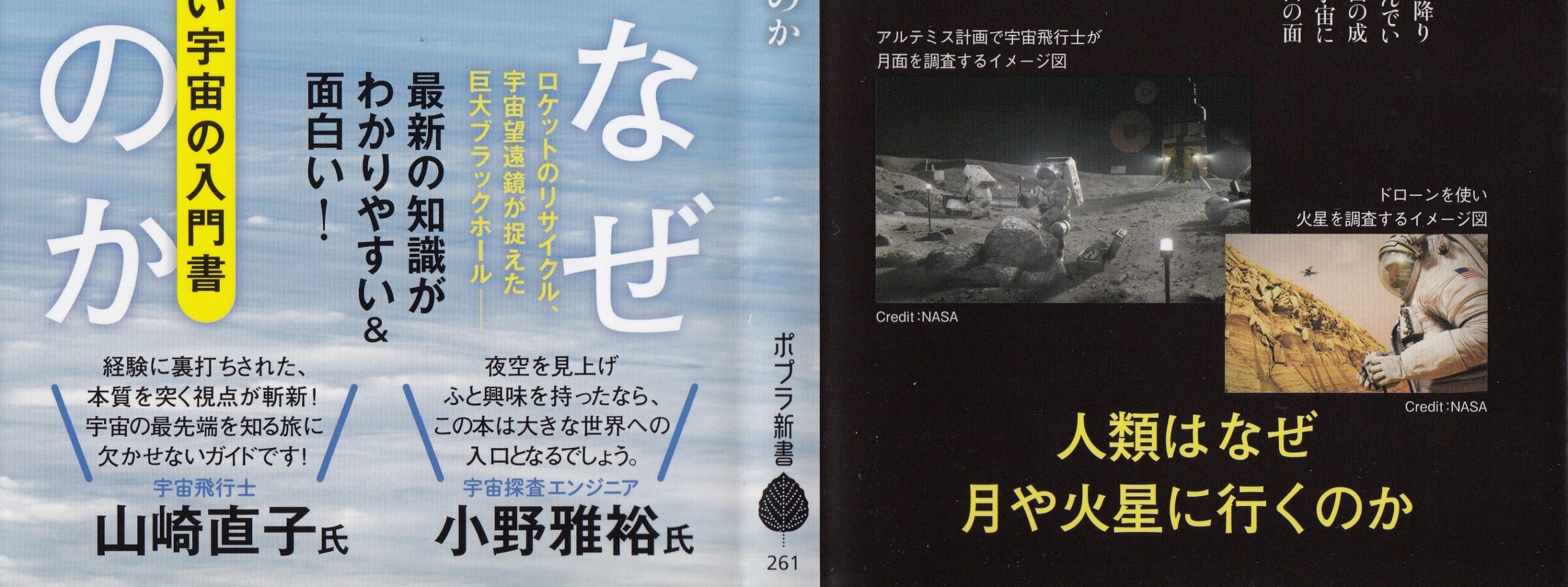火星探査で何がわかってきたのか
地球のように生命が存在できる領域をハビタブルゾーンと呼ぶ。NASAは金星、地球、火星を含むゾーンだとしている。火星の表面は、現在は干からびた砂漠の様相だが、初期の頃には表面に水が存在していたという分析がなされている。水が流れていただろう跡は地表にも地下にもあり、湖の跡も見つかっている。現在でも、火星の南極付近の氷の下には湖があることも突き止められている。
火星探査の中でもNASAの「マーズ2020」というミッションでは、生命がいたのかどうかを調べている。火星の中で水があっただろうと考えられるジェゼロ・クレーターが探査先である。そのあたりの石や岩を採取すると、36億年前の火星の様子がわかるだろうという。
日本からも火星圏に探査機を飛ばし、火星の「月」からのサンプルリターンが計画されており、2026年度の打ち上げが予定されている。火星の周りは、フォボスとダイモスという2つの衛星が周回している。このフォボスからサンプルを取り、地球に持ち帰ってくる計画で、フォボスに降ろすローバーは完成している。
太陽系には「スノーライン」と呼ばれる境界ゾーンがある。太陽系の惑星は、岩石惑星、ガス惑星、氷惑星と並んでいる。地球や火星が岩石惑星である一方で、木星はガス惑星である。スノーラインは、火星と木星の中間あたりにあるとされ、その内側にあるのが岩石惑星、外側にあるのがガス惑星である。
太陽系が形成されていた時期には、スノーラインの外側では、水は氷として存在し、内側では水蒸気として存在していたと考えられている。宇宙空間は圧力が弱いので、水は液体の状態では存在していなかった。岩石惑星には水はなかったが、スノーラインの外側からやってくる隕石や小惑星に氷を含むものがあった場合、地球に氷の形で水がもたらされたという仮説が立てられる。
スノーラインの境界に近い火星の衛星フィボスとダイモスには、スノーラインの外側から氷や有機物が運ばれ形成された跡が残っている可能性が高い。そこからサンプルを持ち帰り、分析することによって、スノーラインの内側にある火星や地球の水がどこからきたのか手がかりが得られる可能性がある。
金星探査で何がわかってきたのか
金星も火星や地球と同じく岩石惑星である。ただ太陽に近いため、灼熱地獄と呼ばれることもある金星は、二酸化炭素が主成分の大気に覆われている。また、硫酸の雲が厚く、太陽光線が金星の表面に届かないほどである。
金星は、2020年にフォスフィンと呼ばれるリンと水素の化合物が見つかり、もしかすると生命が存在する証拠ではないかと注目された。フォスフィンは地球上にもあるが、沼や湿地で発生する可燃性のある有毒ガスで、低酸素環境に住む微生物が生成している。
これまで、木星や土星で、生物によってではなく、高温・高圧によって生成されたフォスフィンが見つかっているので、フォスフィンがある=生命発見とはならないが、MITの研究者チームが金星の生命探査ミッションを立ち上げた。
第1段階は、3分から10分ほど金星の大気圏に突入し、金星の雲を構成する水滴の形状やその化学組成について調べる予定である。その跡、気球を使って滞空しながらの探査活動やサンプルを地球へ持ち帰ることなどが構想に入っている。この金星において唯一の生命探査ミッションは、2025年の打ち上げを予定している。
地球のすぐ内側を回る金星は、地球と大きさや重さが近いために、地球の双子の星とも呼ばれている。そのため金星を知ることで、地球のことが科学的にわかるのではないかと期待されている。
地球と金星の大きな違いは、金星を取り巻く大気の状態である。地球の自転は1日1回だが、金星は非常に遅く自転に243日をかける。しかし、その速度をはるかに上回る高速で大気が流れ、4日で金星を一周する。どうしてそのような動きが起こるのか、地球での気象の仕組みでは説明ができない。この高速大気循環のメカニズムの解明は、日本のあかつきという探査機によって、2021年に画像解析の結果として発表された。
NASAからの金星探査機は2つあり、2030年代に金星に着陸することを目指している。「ダヴィンチ・プラス」というミッションでは、テッセラと呼ばれる金星の地形の画像を高解像度で撮り、地球の大陸のようにプレートが広がっているのか調査する予定である。また金星の大気の組成を詳しく調べることも計画されている。
もう1つのミッション「ヴェリタス」では、金星の周りを回りながら、金星の表面を観測し、金星の地形を3Dマッピングする計画である。金星の全貌を解明していこうとするものである。
2030年代に金星の探査が進む予定で、双子の星の惑星のことがわかると、地球の気象現象や成り立ちも、より正確に説明できるようになると期待されている。