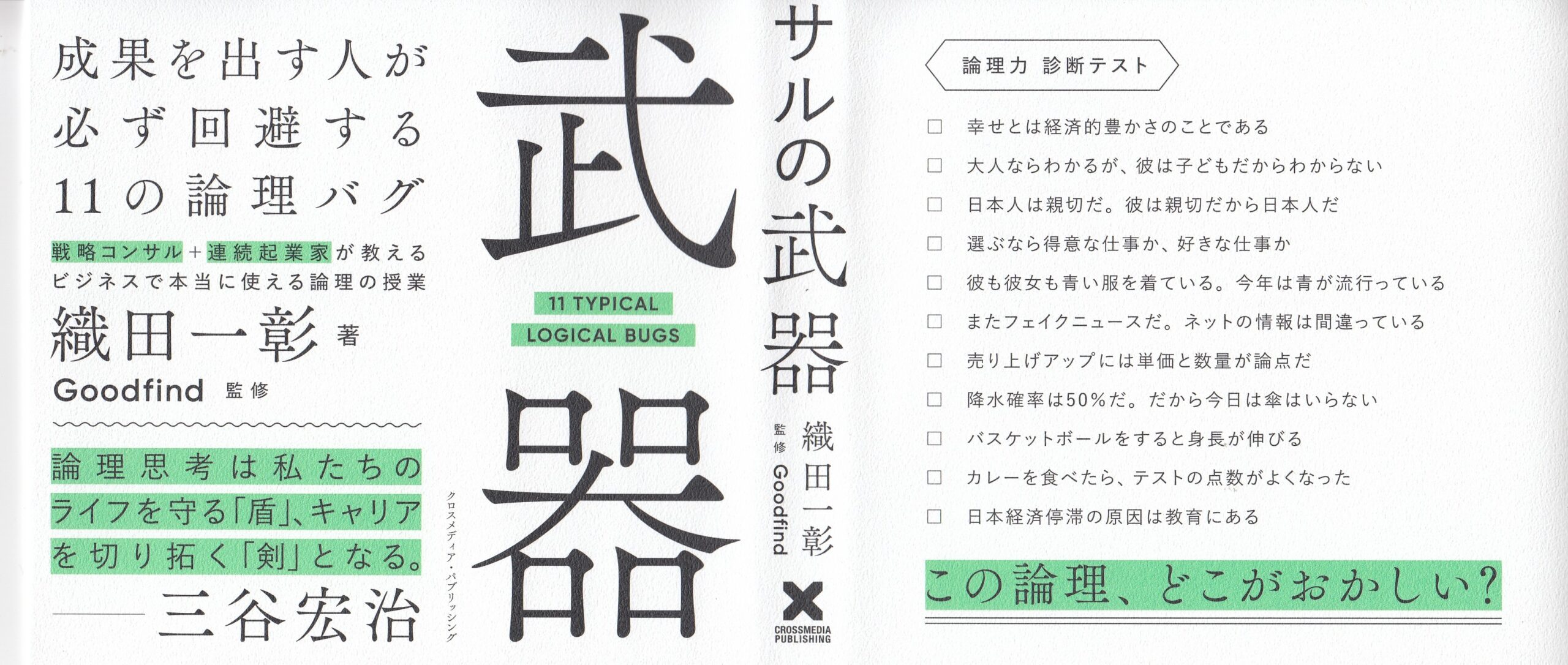答えを導き出せる問いなのかを判別する
論理とは、思考のもとになるルールのこと。ルールとは、多くの人が正しいと認めている法則や定理のことである。論理的に物事を考えることを「(論理的)推論」と呼ぶ。推論の基本形である「AならばBである」というシンプルな一文の中にも、私たちは無意識にたくさんのバグを仕込んでしまっている。「AならばBである」が意味することは、「Bという結果」を導くためには「Aをする」必要があるということである。これは問題解決の大原則で、「原因」と「結果」の関係を明らかにすることで、物事を期待通りに導けるようになる。
「AならばBである」という形は、物事の理由づけや関係性を示す時に非常によく使う。しかし、真と偽という2つの値をとるこの形式には、実は誤りが多く含まれる。世の中にある一般的な問題はマークシートのように答えが1つに決まるとは限らない。私たちは論理というツールを過大評価し、「論理的に考えれば、どんな問題でも答えを出せる」と勘違いしがちだが、そうではない。
問いに答えがあるかどうかを考える時に出てくる概念が、次の2つである。
- 形式論理
考える時に言葉を形式的に矛盾なく使うというルールを持った論理。答えが1つに決まる世界で、主に数学やコンピューター・サイエンスなどの分野で使われている。 - 非形式論理
形式論理以外の論理。正しいかそうでないかを100%決められる「形式論理」に対し、「非形式論理」は一部曖昧さを許容しながら実用的に使われる。
厳密に100%の真偽を判定することはできないが、ある程度の精度で物事を決められるのが「非形式論理」である。エビデンスとして信頼しているであろう研究論文の実験データにも非形式論理が使われている。実験データは、実験の条件などを詳しく記述し、その範囲内での事実なり解釈をまとめている。しかし、将来的に違うデータが出てきた時には、それまでの解釈は誤っている可能性がある。数学の証明のように100%合っている保証はない。
コンサルタントが現状のデータを分析する時は「形式論理」と「非形式論理」を使い分け、どこまでが「ファクト」で、どこからが「アイデア」なのか非常に気にしながら提案をまとめる。その結果「ファクトは何?」と繰り返し問いかける。
注意すべきなのは、推論の正しさと結論の正しさは別物ということ。推論のプロセスが正しかったとしても、前提が間違っていたら、結論が正しくなる保証はない。実態に合った正しい情報を用いて、正しい推論のプロセスで考えることができて初めて、正しい結論を導くことができ、論理的思考を武器にすることができる。
帰納と演繹を理解する
「形式論理」の代表格が「演繹」である。「非形式論理」の代表格は「帰納」である。「演繹」とはルールを組み合わせたり、解釈したりして論理を考えることで、「帰納」とは経験則のようにいくつかの事例からルールをつくる推論形式である。
演繹の世界は例外なく真偽がどちらか1つに決まる。理論的には、非常にシンプルで美しい。しかし、その美しい世界を築き上げるために怪しいものをすべて排除している。そのため、現実世界でそのまま使える場面はそれほど多くない。問題なのは、演繹とその他の論理を混同して、演繹ではない推論もあたかも演繹であるかのように、答えや真偽がきれいに決まると思い込んでいることである。もとの主張の真偽を考える時には、それに当てはまらない例を探してみることが有効である。
帰納とは、いくつかの個別の事例から一般的な法則を見出す推論の方法である。実験や調査の結果から結論を導くことや、日常生活で経験則と呼ばれるものは帰納の一種である。この結論を調べるために、より多くのサンプルを集めれば、結論が正しいかどうかがわかってくる。
帰納的な推論をする時に前提として必要なのは、複数の事象なり事実である。それらに共通する要素なり法則を導く。対象となる事象の数が少ないと、そこに存在する法則を誤って結論づけることがある。帰納的に推論を進める時には、結論が必ずしも正しいとは限らないことを理解する必要がある。
帰納的推論では、具体的にサンプルや実験結果などの根拠を伝えることで、聞き手が推論の道筋を検証できる。帰納的な推論でよく見られるエラーは、少ない事例や情報から一般化する範囲を拡大しすぎることである。
実生活で推論する時には、帰納と演繹の両方を使う。演繹は論理的には強力だが、まず仮定がないと始まらない。そのため、帰納的な結論を演繹における仮定として使うことが多い。しかし、帰納的な結論は後から変わる可能性もある。その場合、演繹においては仮定が偽であるケースでは有効な推論ができないため、論理的には何も結論が出てこないことになる。「ルールが何を根拠にできているか(帰納)、そのルールを正しく用いているか(演繹)」が大事である。