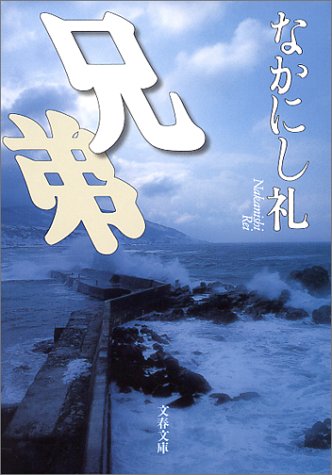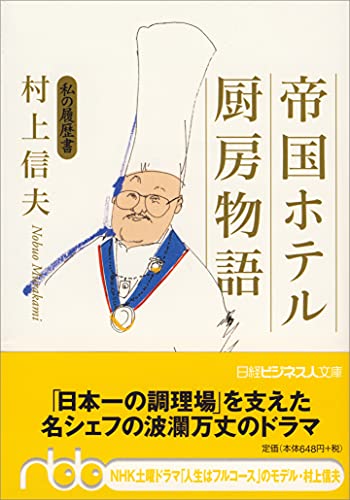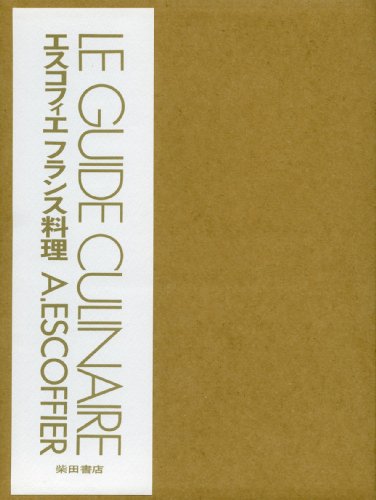小学校二年生の漁師
父は、北海道の日本海側にある増毛という漁師町の漁師だった。網を流したり、引き揚げたりしている父の横で手伝うのが自分の仕事で、小学2年生くらいから、毎日父と一緒に船に乗っていた。小学校の高学年になると、魚市場に売りに行くのも、自分の役目になった。一斗缶にウニやアワビを詰めて、朝6時半の汽車で市場に運ぶ。留萌の魚市場で、背負ってきた魚を大人に混じって競りにかけた。
料理店に持ち込むことを憶えたのもこの頃だ。時化でアワビが1つか2つしか獲れず、数が少なく競りにかけられなかった時、バス停裏の食堂の母さんに料理屋を教えてもらった。アワビでもウニでもモノが良ければ料理屋に直接持って行った方が高く買ってくれた。裏口から覗く厨房は別世界だった。厨房で働く料理人たちは颯爽としてカッコ良かった。この時、料理人という職業を初めて意識した。
毎日働く以外の暮らしなんて知らなかった。食べ物は、喉が渇けば、畑のトマトをもいで食べた。船の上で腹が空けば、刺し網から外したエビの殻を剥いて口に放り込む。ウニの殻を割り、甘みの濃い卵巣を指先ですくって啜る。冬の浜で焚き火にあたりながら焼いて食べることもあった。海で獲れたものは何でも食べた。タコ、イカ、ボタンエビ、シマエビ、甘エビ、ニシン、サケ、アイナメ、カレイ、ヒラメ、ソイ。今考えればご馳走だが、子供の頃はただのありふれた日常の食べ物でしかなかった。中でもホヤが大好きだった。甘味、塩味、酸味、苦味、旨味。味の基本要素がすべて含まれている。子供の頃からそんなものを食べていたら、嫌でも味覚は鍛えられる。後の仕事を考えれば、学校で勉強するよりもはるかに重要なことを生活から学んでいた。
黒いハンバーグ
中学を卒業して、札幌の米屋に住み込みで働くことになった。仕事が終われば学校が待っていた。鶴岡学園北海道栄養短期大学併設の別科調理専修夜間部。高校卒の資格はもらえないが、とにかく学校に行けるのが嬉しかった。1年半通えば調理師免許も取れる。
仕事が終わったら、急いで夕食を食べて学校に行く。その夕食が楽しみだった。米穀店のお嬢さんが作ってくれた。栄養士の資格を持っている人で、食卓にはいつもハイカラな料理が並んだ。料理らしい料理を食べたのは、それが初めてだった。1番の衝撃はハンバーグだ。肉料理と言われたが、知っている肉は年1回食べたジンギスカンくらいだった。
お嬢さんは「グランドホテルのハンバーグはこんなもんじゃない」と言った。それが札幌グランドホテルを知った最初だった。北海道で最も格式の高いホテルだ。お嬢さんから聞いて、その瞬間に自分はグランドホテルのコックになって、日本一のハンバーグを作ると決めた。札幌グランドホテルは人生の目標になった。
グランドホテルの就職試験を受けるには高卒以上の資格が必要だった。そればかりはどうにもならなかった。しかし、どこかに抜け道はあるはずだ。なんとかなると自分の勘が告げていた。
人生の分かれ道
鶴岡学園調理専修夜間部で、テーブルマナーの実地研修をすることになった。その会場が札幌グランドホテルだった。研修の最後にホテルの人が厨房を案内してくれることになった。列の最後尾につき、洋食厨房まで来た時、隙を見てステンレスの調理台の陰にしゃがみ込んだ。一番偉そうな人を探し、「ここで働かせてください」と大きな声で言って、頭を下げた。
連れて行かれたのはホテルの社員食堂の調理場だった。「社員にはしてやれないが、ここで働く気はあるか?」と言われた。こうして札幌グランドホテルの社員食堂の飯炊きになった。グランドホテルで働けるかどうかで、自分の人生は決まると思い込んでいた。厨房に隠れたあの日が、人生の分かれ道だった。
言われたことをするだけなら誰にでもできる。仕事を手伝うのは本来はそういうことではない。料理をしている人には、他人に指示を出している暇など本来はない。助手は何も言われなくても、先を読んで動かなければならない。社員食堂の調理場では、飯炊きだけでは物足りなくて他に手伝えることは何でもしたが、それでも身を持て余した。社員食堂だから夕方の6時にはすべての仕事が終わってしまう。
地下の洗い場にはいつも洗い物がたまっていた。宴会では何十人何百人分の料理を一斉に出さなければいけないから、調理中に洗っている暇などない。飯炊きが終わると洗い物をやった。毎日洗い物を続けて半年が過ぎた頃、特例で社員にしてもらえた。
メインダイニングの厨房に配属されたのはいいが、下っ端は朝から晩まで暇なくこき使われる。料理の修行は夜更けにするしかなかった。真夜中の厨房でフライパンを振って、地下の仮眠室のベッドで眠る。翌朝は厨房に一番乗りで下働きの仕事に精を出し、夜中にはまた料理の訓練をする毎日だった。
1つの技術を憶えるたびに、厨房でやらせてもらえることが増えた。料理人の世界は、学歴も年齢も関係ない。仕事ができるかできないか。できさえすれば、どんどん重要な仕事を任されるようになる。1年後にはソースの味を決める重要なストーブ前の担当になり、厨房の仕事は何でもできるようになっていた。
苦労する覚悟があれば、どこかに居場所は見つかる。見つけた場所で一所懸命にやれば道は開ける。自分にそれしかやれることがないなら、楽観的にやり続けるしかない。みんながやりたくないことを、機嫌良くやることだ。