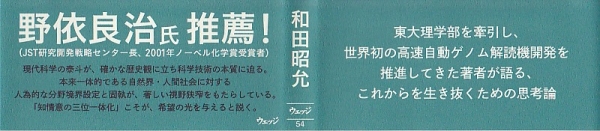サイエンス思考とは
サイエンス思考とは、物事を考える時の基本であり、日常のどんな場面にも応用できる考え方である。まず、理解しようとする、あるいは作ろうとする「全体」の範囲を、どこまでにするか決める。その上で、中に含まれるいろいろな「要素」を探し出し、すべてを頭に浮かべ、それらがどのような「相互作用」をし合って、全体を演出しているかを理解していく。ここで忘れてはならないのは、全体が置かれている「環境」との相互作用。つまり全体は「切り出した」とはいうものの、完全に周囲と切り離されて独立している訳ではない。
要するに対象を「全体」「要素」「相互作用」からなる三位一体のシステムと考える。それに「環境」の影響を入れて理解し、製作する。あるいは「全体・要素両方の理解の最適化」に持っていくのが、一般的なサイエンス思考である。
全体を広げ過ぎると内容がぼやける、しかし、狭くするとバランスが崩れる。何よりも発展がない。狭い話題は、問題がシャープに絞れるから議論は楽だ。一方、広く考えるには異質の物事の軽重を問わなければならないから難しい。
サイエンス思考の根幹
サイエンスは、自然界のデータが取りやすいものから始まった学問。最初は星空を見る天文。それがだんだん複雑なものを相手にするようになり、今のような幅広い対象を考える学問として広がってきた。観察してデータを取って理解し説明をする、というサイエンスの体系は昔から変わっていない。理解すると同時に、先を見通す事もできる。サイエンスは、物事を考える時の強力で万能なツールである。「サイエンス思考の根幹」とは次の通りである。
①対象をよく観察する
②正確で十分な情報(データ)を取り出す
③データ間の因果をつなぐ論理を見つける
④対象を理解し説明する最適の解決・解答(仮定・モデル)を出す
⑤高度に技術化された社会を、その仮定、モデルに基づいてスムーズに運転する
⑥将来を見通して予想、予言し、未来を開拓する
自然現象だけでなく、人間心理や社会現象のデータも取りやすくなった今、サイエンスの考え方は、経済や金融、人間社会一般にも通用するようになった。
学問の原点
「秩序の発見」が、すべての学問の原点にある。なぜなら、秩序の背後には何らかの力が働いており、それを支配している原理や法則が必ず隠れていて、それこそが学問が知りたいと目指す相手だからである。
「秩序」とは、物事の関係がもたらす条理と規則性である。物事には、科学的、社会的、歴史的、芸術的、文学的など様々な方向があり、その切り口には大中小の「要素」群があって、それらの関係(相互作用)に秩序がある。秩序を持った構造全体を「システム」と呼ぶ。森羅万象は、それ自体が究極のシステムであると同時に、大小様々なシステムの集合体である。
わからないことを怖れない
研究は、蛸壺に頭を突っ込んだようになると、考えが伸びないどころか縮んでしまう。新しいアイデアを出すにはお互いの「暗黙的な知」を引っ張り出して形ある「形式化された知」として共有する事が必要だ。そのために、自由闊達な会話と、それができる雰囲気醸成の溜まり場が不可欠になってくる。特に生命王国は暗黙知の宝庫だからである。
「天才は一を聞けば十を知る」と言われている。でも、何もない状態から九が生まれてくる訳ではない。今まで頭の中をふらついていて行き場のなかった九の暗黙知が、一を聞いた事で理解のきっかけを見つけ、その周りに集まってくる。そして、自分の新しい知識としてまとまってくる。だからこそ、わからない事を怖れてはいけない。できるだけたくさんの暗黙知を頭の中に入れておく事が大事である。
サイエンス思考の起承転結
サイエンスとは、森羅万象を相手に「起=見つける」「承=知る」「転=創る」「結=解る」、そして次のための「起=蓄える&伝える」を筋立てていく事である。「起承転結」の後に再び「起」が来て、発展ループができ上がる。
サイエンスは「全体の構造や性質は、部分の相互作用が演出する」といういわゆる要素還元主義である。森羅万象から興味のある課題を「ひと切れ」見つけて考える。それが「起=見つける」である。
対象の発見
研究とは面白いテーマを発見して切り取るところから始まる。問題とすべき対象を見つけ出し、その考察のために必要と思われる範囲を、とりあえず明確に決める。次に、研究対象について必要なデータを得るための実験と観測をする。「全体」「要素」「相互作用」に関する情報を収集する。ここが理解の出発点になる一次知識である。
知る
「全体理解」を進めるためには、その要素となる一次知識を集めて「部分理解」の一群を作る。具体的には、イメージ、データ集、グラフ、図、機器、機械、仮定、モデル等がある。一次知識は数多くの断片なので、一度にまとめる事はできない。従って、納得できる小さな組合せをいろいろ作ってグループ化していく。
創る
ここで大事な事は「智恵」を働かせて「知識」達を関係づけていく事だ。こうしてできあがっていくのが。二次以上の知識である。新しい智恵も生まれてくる。ここからは、他人にもらった知識ではなく自分の知識だ。しかし、それを既存の知識と比べると不具合が見つかったり、他の「部分知識」と矛盾したりするのが普通である。そこでまた考える事で、高次のステージに上がっていく。
解る
「部分理解」を矛盾なく整合させていくと、次第に知識の次元が上がり、まとまっていく。そして「全体理解」へと進む事ができる。作り上げられた「仮説」や「モデル」は試運転しなければならない。
自分が既に持っている知識や、実験や観測の結果が、矛盾なく整合がとれる事を確認する。そして、既存の知識体系の中に、自分が出した回答が無矛盾性、斉一性を持って組み込まれる。これで「解った」事になる。
わかるとは何か
サイエンスは、物事の関連を矛盾なくはめ合わせて大きな絵にまとめていくジグソーパズルみたいだ。そこではサイエンスの知識が「事実と理論の整合性」「体系の無矛盾性」を象徴するかのように、すき間なくはめ込まれている。
この知識体系は未完成である。科学者は実験や観測の結果を抱えて、その行き先を一所懸命に考える。矛盾なくはまる縁が見つかると「わかった!」となり、サイエンスの体系が広がっていく。
知識やデータが手元に山積みになってこそ、理解がはかどる。だから発明や発見には、豊富な知識の蓄積が極めて重要である。