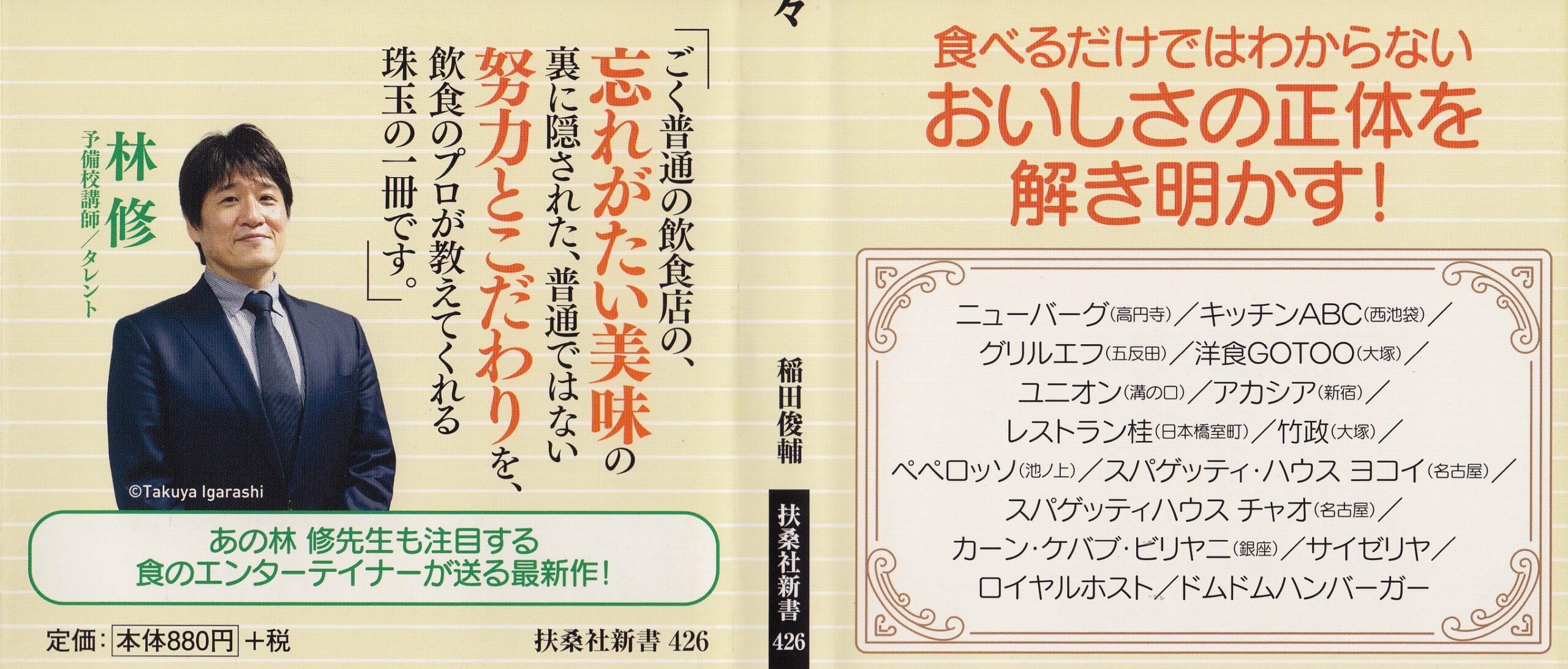今なお530円の価格を守る歴史あるハンバーグ
高円寺の小さな洋食店「ニューバーグ」は昼も夜もお客さんが引きも切らない。でもそれは「繁盛」とは少し違うのかもしれない。看板商品のハンバーグは530円で、ライスとみそ汁がつく。お客さんが常に入り続けないと成り立たない商売だ。
すべてが手作りなら、なおさら店を維持するための売上を確保するには工夫がいる。ハンバーグを営業前やアイドルタイムにまとめて焼いておき、次々と来店するお客さんに電子レンジを使って素早く仕上げて提供するオペレーションは、合理的なやり方だ。
創業当時、庶民にとってまだ高嶺の花だった「ナイフとフォークで食べる洋食」を大衆食堂並みの安い価格で提供したニューバーグは評判を呼び、最盛期は7店舗も展開。ところが、ファミリーレストランなどの台頭で「気軽な洋食」はここだけではなくなった。一軒、一軒と店舗が閉店する中、高円寺店を買い取ったのが現在店を切り盛りする平井誠一さん・仁さん兄弟の父だ。
「自分が作ったものをうれしそうに食べてくれるお客さんを見ると手は抜けないし、もっとおいしくするにはって、自然と考えちゃうよね。じゃないと毎日面倒くさい仕込みなんてやってらんないしさ」
製造部門の分離という今風のシステムを早くに確立したニューバーグ。しかし、個人店の本質とは結局のところ、こんな部分にあるのだろう。食べ手1人1人の表情がそのお店を形づくるのだ。
フランス料理のタイムカプセルのような老舗
洋食のルーツはフランス料理である。明治、大正、そして少なくとも戦後しばらくまでは「西洋料理」と呼ばれ、それは「フランス料理」とほぼ同義であった。だから、現時点で50年以上の歴史を持つ洋食屋の中には、「フランス料理」を標榜している店も少なくない。
フランス料理というのは伝統を大事にする一方で、時代とともに大きく姿を変えている料理体系でもある。例えば、かつては花形であった「デミグラスソース」は、現代フランス料理ではまず正面切って使われることはない。一説によるとそれはあまりにおいしく完璧すぎて、ややもすると料理がすべてそこに収斂してしまうという理由で、ある時期からフランス料理界が一斉にそれを手放したとも聞く。
そんなデミグラスソースだが、日本の洋食界では昔も今も常に主役。洋食というものは、つまり100年前のフランス料理を今に伝えるタイムカプセルでもある。
グリルエフは、フランス料理店として1950年創業。初代シェフの斎藤公男さんは「上野精養軒」や今でも伝説として語られる「レストランエーワン」を経た、いわば当時のフランス料理界におけるエリート中のエリートである。グリルエフは五反田の街で一番高級でハイカラなレストランであり、夜ごとに財界人や文化人が集った。そんな店に入店したのが現オーナーシェフの長谷川清さんである。
「メニューは一切変えるつもりはないし、レシピも変えない」
長谷川シェフはそう断言する。なぜなら初代シェフが作り出したそれは最初から完成されたものであり、現在それを作る自分は、味見するたびにそのことを確信すると。そして、お客さんもそれをずっと支持してくれている。変える理由は何1つないとも。
「斎藤さんはその技術のすべてを自分に教えてくれた」と長谷川シェフは述懐する。メニュー表は、当時の斎藤シェフによる手書きをコピーしたものだ。価格だけを書き換えながら、今もそのまま使用しているという。
お店と料理と現代の料理人を通して過去の人物像に出会える。これもまた歴史ある店を巡る楽しみの1つである。
独特なスタイルを持つ洋食店
創業60年になろうとする新宿の洋食店「アカシア」は典型的な洋食屋のスタイルとははっきり異なる。この店で圧倒的に人気のあるメニューは「ロールキャベツシチュー」だ。ポークカツも目玉焼きハンバーグもナポリタンもないし、定食にみそ汁はつかない。
開業当初のアカシアは、ステーキや海老フライを中心とする「高級洋食店」だった。しかし高価格設定が災いしたのか、2、3ヶ月と泣かず飛ばずの状態が続く。その時に創業者である鈴木邦三さんにあるアイデアが閃いた。それが現在に至るまでアカシアの看板メニューとして多くの人々に愛され続けているロールキャベツである。
ロールキャベツは、少量の挽き肉さえあれば、あとは野菜だけで賄える家庭向きの料理。邦三さんにとってロールキャベツは、子供の頃から慣れ親しんだ「家庭の味」だった。このロールキャベツを、ライスと組み合わせたセット、つまり少年時代に家で食べていたのと全く同じシンプルなスタイルで提供した。
高級洋食店だったはずのアカシアに突如登場したロールキャベツとライスのセットは、120円という安値で提供された。それは当時のタクシーの初乗り料金と同じだった。「洋食にしては庶民的」なイメージを逆手にとって、それをあくまで庶民的な料金で売り出し、瞬く間に大人気を博した。