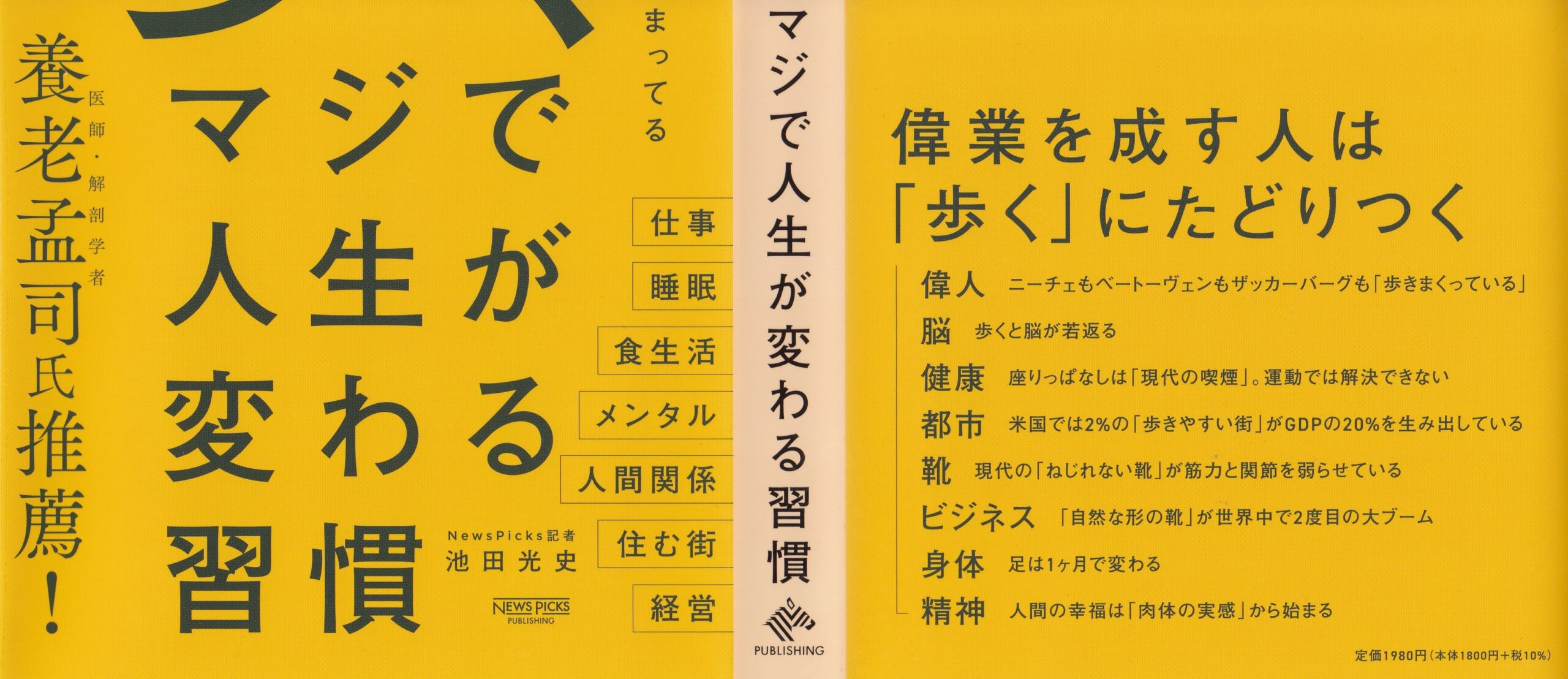歩くことと脳の関係
人が歩くことは、脳が働き出すということと深く関係している。過去の偉人たちは、人間が創造性を発揮することにおいて、歩くことの重要性に気づいていた。そして、現代の科学も「歩くと脳が鍛えられる」ということを示唆している。
脳の記憶や学習をつかさどる部位「海馬」は、歳を重ねるごとに毎年1〜2%のペースで縮んでいくことがわかっている。ところが、よく歩くと、この海馬の体積が大きくなることが明らかになった。歩くことによって増加した海馬の体積は、血液中のBDNFと呼ばれる物質の増加と相関している。BDNFは、脳の栄養素のような物質で、これが海馬の中で作用し、新しい神経細胞を作り出したり、既存の神経細胞の枝分かれを促して成長させる。
身体は歩くことを前提に設計されており、歩くことで、脳は自然と鍛えられ、健康な状態になるようにプログラミングされているのかもしれない。
そもそもなぜ、歩くと脳が働き出すのか。この問いの立て方自体がズレている可能性がある。現代人の脳は、むしろ常に強い覚醒・ストレス状態にあり、そもそも働きすぎている。そうした現代人が自然に触れると、人としての本来あるべき姿に戻る。
私たちは脳を効率よく働かせるかばかりを考えるが、本来はリラックスさせることの方が求められている。普段、人間は複雑なことを考え、頭が主導権を握っている。しかし、歩いて全身を使い、身体優位へシフトすることで、頭が空っぽになり、思考が整理されるのだ。
人類は歩かなくなった
歩くことは健康にいい。その主な効果は次の通りだ。
- 血糖値や血圧が下がる
- 長生きする
- がんや心疾患リスクが下がる
- 不眠が改善し、ストレスも減る
- 脳卒中リスクが下がる
こうしたテーマの論文を読んでいく中で感じるのは、歩くと健康にいいのではなく、人類は歩かなくなったから、様々な不具合が起きているのではないか、ということだ。
文明の発展とともに、人類は歩かなくなった。産業革命以前、人類は1日3時間ほどしか座らなかった。それが気づけば都市居住者となり、私たちは1日10〜15時間も椅子に縛られている。現代のテクノロジー、即ちテレビやパソコン、コンピュータゲーム、車などの出現によって、人類は歴史上、かつてないほど座っている時間が長くなっている。
しかし、私たちの身体は本来、そのように設計されていない。人間の生き物としての設計は、少なくとも20万年は変わっておらず、狩猟採集時代から人体は特段アップデートされていない。だからこそ、長時間の座位は死亡リスクを高めるのである。
頭と手を使うだけで済む都市生活は五感を駆使することの大切さを忘れさせる。不快や不便があっても、ただカネを払いさえすれば、どこかに必ず解決策の供給源がある。このことは、自分が本当に欲しているものへの感覚をますます遠ざけてゆく。
テクノロジーや経済の未来は、人間の身体性という視点を抜きにして語れない時代に突入していくのではないか。人間の幸せは、動物として快調かどうかにかかっている。その生きた心地というものは本来、身体感覚と密接に関わっている。それを置き去りにし、身体性を奪う社会システムは長く続かない。今後、テクノロジーの進化とともに、身体性をいかに取り戻すかがイシューになる。
現代人の足は壊れている
解剖医でもあったレオナルド・ダ・ヴィンチが、人体の中で最も注目したのは「足」の構造だった。足の骨の数は左右合計で56個あり、全身の骨約206個の内1/4を占める。骨の数が多い分、関節や筋肉の数も多い。そして、着地の時には衝撃を吸収して、地面を蹴り出す時には硬くなる、いわば複雑な「精密機器」だ。
中でも重要なのは、土踏まずのアーチで、走る時には体重の2倍の荷重が身体にかかるが、まるでバネのように作動して、その衝撃をアーチと足首だけで54%も吸収する。さらに足はセンサーの役割も果たしており、人体で唯一、大地とつながる感覚器でもある。圧力や振動、足底にかかる力の変化といった刺激からの情報を脳に伝え、これに資格などを融合させた膨大な情報を蓄積することで、私たちの身体は倒れないようにバランスを取っている。
脳は、過去の経験や現在の足裏感覚に基づいて次の身体の動きを予測する。ところが、分厚く曲がらない靴に履き慣れていると、脳に対して感覚情報が十分に伝わらず、その結果、脳は地面の状態や身体の微妙な動きを予測するのが難しくなる。つまり、現代の靴を履いて歩くと、本来の身体機能を使えないまま、歩き続けることになる。
現代の靴は、いわばギプスやコルセットのようになっている。私たちの足は、思った以上に弱体化しているとみなされ、ガチガチに機能性で固めた靴ばかりが世に溢れている。こうした靴は、壊れた足を一時的にサポートしてくれるから「歩くのは楽」かもしれないが、決して足が強くなっていくことはない。