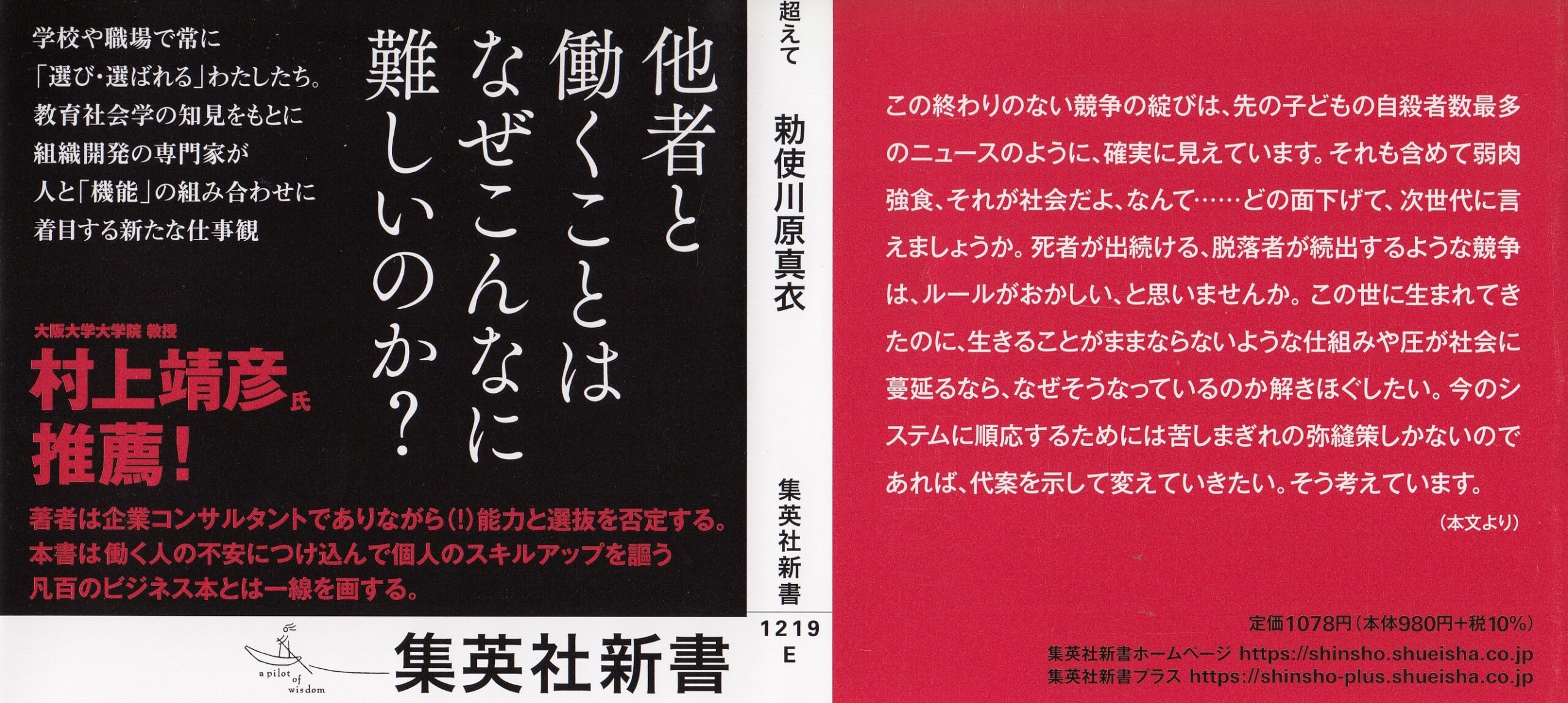能力主義は平等な仕組みなのか
生きるために必要なあらゆる資源には限りがある。そうなると、いかに「分け合う」かが問題になる。それに対して合理的な説明なしに、権力で強制的に従わせてきたのが古くからの統治。その後に「生まれが違うから人生も違う」と押し切ってきたのが近代以前の身分制度と言える。
強引な仕組みだから「本人がどうすることもできない理由で、分け隔てるのは差別だ」という主張が出てくる。ここで体制側は、生まれではなく能力で個人を「分ける」ことで、正当な民主制だと思わせる巧みな論理を編み出した。
「能力」の違いによって、人々を分け、その差を基準にして、限りある資源を「分け合う」という原則。できる人はもらいが多く、できの悪い人はもらいが少なくても仕方ないという考えは、社会の普遍的な掟のごとく定着した。果たして個人の「能力」によって人が人を「選ぶ」ことを是とする「能力主義」ならば平等な仕組みなのか。
能力主義の問題点
選ばれる人・選ばれない人の違いは「能力」の違いであって、それによって富んだり貧したりすることをやむを得ないとする見方について、実証的に待ったをかける代表格が教育社会学である。教育社会学者たちは「能力主義」に関して、次の3つの論点を問い質している。
①「能力」という虚構
能力というものが、個人の体内に内蔵されているという前提で、「正確に測る」だの、「開発・伸長する」など、そもそも可能なのか。
②「能力」という不平等の再生産
「能力主義」の「本人次第でいかようにも人生を選べる」というのはプロパガンダに過ぎず、実態としては、親の階層を子が受け継ぐ傾向が可視化されている。
③「求める能力」の止まらぬ抽象化
かつて「学力」を求められた時は、学校の勉強を一生懸命やれば、それなりの成果が出せた。しかし、現在は社会で活躍するには、勉強だけできても仕方がないとされ、「コミュ力」「人間力」「生きる力」といった抽象的な能力が求められている。
こうした論点から、教育社会学者は「能力主義」が社会の配分を決める、との一般的な社会の認識について、見直しを迫っている。
個人の能力から他者との関係性へ
私たちのパフォーマンスを左右しているのは自分の能力だけによらない。言動の「癖」や「傾向」は個人個人で違いがある。その「持ち味」同士が周りの人の味わいや、要求されている仕事内容とうまく噛み合った時が「活躍」であり、「優秀」と称される状態なのではないか。周囲の人たちの状況や、タイミングなど、偶然性が多分に影響している。
そのため、固定的で、実態を証明しているかのような面を下げた「能力」で人を語ることは、不十分である。良し悪しや序列つきの能力ではなく、個人が持つ「癖」や「考え方の傾向」をある程度把握して、それに合わせて周りの人との組み合わせ方や、仕事の内容、与え方、進め方を調整する。それこそが個人の能力に問題を抱えるとする組織が、袋小路から抜け出すための手立てである。
「個人」の良し悪し・能力の高低に拘泥せず、チームとして互いが発揮しやすい「機能」を持ち寄ることで、全体としてうまくことを運ばせることが、組織としての成果である。複雑化した社会にこそ、どの人の持つ「機能」も必要とされている。多様な「機能」を1人の個人の能力に求めるのは、安直すぎる。自分を自分として生きる人それぞれを組織が受け入れ、組み合わせの妙によって、どうにか活躍してもらうこと。これが脱・能力主義の土台である。
まずは「自分たち各々が持ち味を持ち寄って、どうにかやってきた」ということを吐き出してもらい、耳を傾け、承認し合うこと。これが、個人の能力から他者との「関係性」にフォーカスしていく際に、根源的に必要になる営みである。他者と働くとは、「他者の合理性」を承認し合うために、吐露できる場があってはじめて為せる。
関係性という概念は、個人の能力論と比べて、水物のように揺らぎがつきまとい、圧倒的にわかりにくい。個人の能力を測定可能、比較可能、伸長可能なものとして扱い、「あいつはダメだ」「こいつは使える」とやっている方が、体制側にとっては好都合である。まずは企業、労働社会こそが、「脱・能力主義」、組織開発的視座に変わっていくことが期待される。
働くということ
私たちの社会は「自立」を目指すばかりに、本来組み合わさってなんぼの人間を「個人」に分断し、序列をつけて競争させることを学校や職場でやり過ぎた。そこから生まれたものは、多くの人の「生きづらさ」である。
「自立」「自助」の価値が、不用意に押し上げられている。能力をより高く身につけた人が「自立」して生きれば、「よりよい社会」になるのではない。私たちは有能になることや、自立すること、人と競争することのために生きているわけではない。人と人が組み合わさって、助け合うことが生きることである。