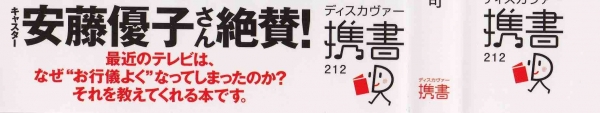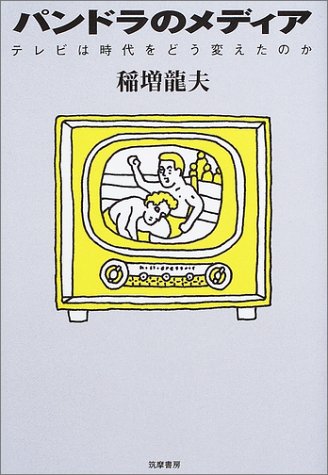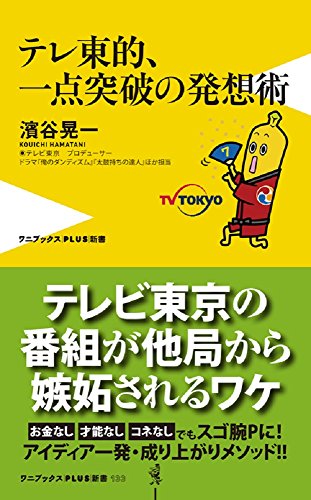楽しくなければテレビじゃない
昭和から平成に移る1980年代末、最も勢いのあった民放はフジテレビだった。新しく試みる番組が次々と当たり、手がけるイベントはグループあげてのPRでいつも盛り上がった。それから30年、勢いを失って最も苦しんでいるのがフジテレビだ。
80年代後半、制作会社が、番組の企画を売り込みにテレビ局に行った時、面白ければフジテレビでは担当者が即決で話がまとまった。一方、TBSは会議にかけないといけないので、なかなか決まらない。制作会社にとって自信のある企画は、まずフジテレビに持ち込まれるという循環が生まれていった。新興のフジテレビが80年代初めに視聴率でトップに立ち、逆転された老舗のTBSはますます水をあけられていった。
フジテレビの失速
フジテレビはノリのいいテレビ局だった。バブル期には制作費を他局以上にかけ、バラエティー番組などでビートたけしや明石家さんま、タモリら大物タレントをレギュラー番組に起用した。同時に、若手の脚本家と俳優を大胆に起用したトレンディードラマは、若い女性の支持を集めた。自動車レースの最高峰・F1の独占中継、実験的な深夜番組、積極的な映画制作など、他局よりいち早く動いては、ブームを巻き起こしていった。
82〜93年まで、フジテレビは全日、ゴールデンタイム、プライムタイムという3つの時間帯で視聴率が首位となる「三冠王」に輝いていた。しかし、94年、日本テレビに三冠王を奪われると、03年まで2位に甘んじた。そして、04年に再び11年ぶりに三冠王に返り咲いた。
トップの座を奪い返した00年代後半から、フジテレビの編成部門で、ある変化が起きたと言われる。以前は、番組の企画を実質的に決めていたのは編成部副部長だった。それが局長クラスの権限が強まり、担当者による即決といった権限委譲は許されなくなったという。制作現場での即決は、コストの面で甘さを生みがちだ。1つ1つの企画を制作費も含めて精査すれば、コストマネジメントは徹底する代わりに決定までのスピードは遅くなる。
フジテレビの失速の遠因は、こうした社内の組織の変化にこそあったように思える。かつて名声や栄誉を持たなかったテレビ局が前例のない手法で挑戦して成功を収めたものの、再び逆転された。再上昇を目指す時、先行する局と似たスタイルをとって結果を出した。成果を獲得する代わりに、現場が自由奔放さを謳歌する闊達さを手放してしまった。つまり、フジテレビが「普通のテレビ局」となってしまったのだ。
04年に取り返した三冠王は10年を最後に失ってしまった。トップの日本テレビを追いかけるどころか、12年には3位、16年には4位へと転落した。18年にはやや回復の兆しが見えたものの、順位を上げるまでには至っていない。
マーケティングの日本テレビ
平成が始まってから20年間、視聴率のトップ争いを繰り広げてきたのはフジテレビと日本テレビだった。斬新な企画や時代を感じさせる作品など番組の革新性という観点から見れば、記憶に残る番組はフジテレビに多かった。
日本テレビは、視聴者が見たい場面をCMの後に回す「山場CM」など、視聴率をテクニカルに引き上げる工夫に長けていた。55分から番組を始め、他局が定時にCMを入れている間に視聴者を誘導したり、クイズで解答を提示する寸前にCMを入れザッピングを避けたりと、徹底的に視聴者の生理や視聴行動を読んだきめ細かい戦略技術を編み出した。
こうしたマーケティングにこだわる日本テレビが14年から視聴率1位を保っているのも、平成末期の時代性を象徴している。