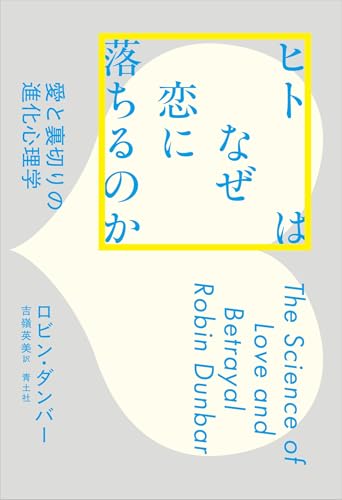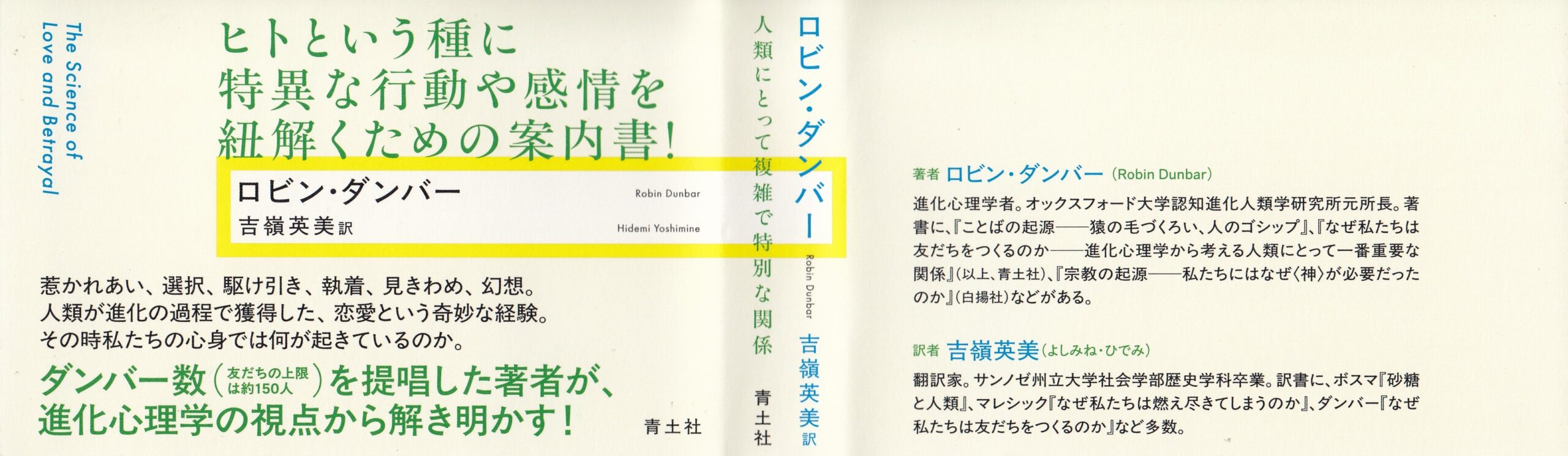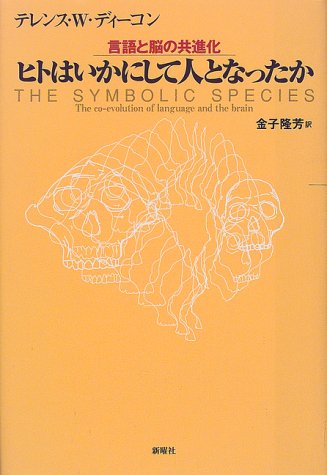恋愛という感情には生物学的根拠があるのか
生きていれば誰もが恋心に囚われる。私たちが恋愛と呼ぶのぼせた気分は、多くの動物が交尾相手に対して抱く感情より激しく、持続期間も比較的長い。通常、初期の熱愛段階は12〜18ヶ月続くが、さらに何年間か落ち着いた形で続くことも多い。
人類の歴史を通してすべての文化、時代の人々が恋に落ちてきた。恋に落ちるという経験が、人類に共通なら、そこには生物学的根拠と生物学的機能があるのではないか。
私たちの中に湧き上がってくる内なる思いを作り上げる感情は、意識的で言語にアクセス可能な脳とうまくつながっていない。そういう感情は、どちらかというと非理的的で動物的に反応すると思われる右脳に属している。つまり、恋愛にまつわる様々な感情は、深いところに埋め込まれた感情の仕組みから生じている。その仕組みは非常に古いもの、言語を習得するはるか以前の私たちの先祖から受け継いだものだ。
恋愛関係の進化的起源の本質
哺乳類では、一雌一雄制の配偶システムは非常に珍しい。哺乳類のすべての種の内、一雌一雄制の種は約5%。霊長類で一夫一婦制を採用している種は15%だ。
壮大な進化の物語の中で、ペアボンドが進化した理由は4つしかない。この1つ1つが異なるペアボンド行動につながるため、それを知れば恋愛関係の進化的起源の本質を理解する一助となる。
①配偶者防衛仮説:オスがメスとの交尾を独占し、生まれた子の父が自分であることを確実にするため
ペアボンドはオスにしかメリットがないため、その関係を維持しようと努力するのはオスの方だ。この行動をするのが小型レイヨウ、クリップスプリンガーで、世界で最もペアボンドが強い種だ。
②捕食リスク仮説:子が捕食者に殺されるリスクを減らすため
オスが提供する防衛はオスとメスの両方にメリットがある。メスは、自分の命が守られるし、オスはもしパートナーのメスが死んだら繁殖できないからだ。
③ボディガード仮説:子が他のオスに殺されるリスクを減らすため
自身と同じ種の別のオスによる捕食では、赤ん坊や幼い子が餌食になることが多い。オスによる子殺しが頻発するのはサルや類人猿で、その理由は主に妊娠と授乳の期間が長いことにある。ヒトを含む哺乳類のメスは、子が乳離れするまで、次の子をつくれる状態に戻らない。そのため、新たに現れたオスから見れば、子を排除すれば、通常よりずっと早い時期から繁殖を始めることができる。メスにとっては、ボディガードとして自分と子を捕食者や他のオスから守ってくれる特定のオスとペアになるという選択肢が魅力的になる。
④オスが子育てに貢献できるようにするため
これは、両性とも同じように子育てができること、少なくとも一方が子育て、もう一方が母親と子のための食料調達というように役割分担ができることが前提だ。前者の前提にほぼ当てはまるのが鳥類だ。後者は、ごく少数の哺乳類が実践しており、最も知られている例がイヌ科の動物だ。
従来、ヒトのペアボンドは両親が揃って子育てするために進化したとされてきた。全ての伝統的社会がそうであるように、女性は育児を担い、男性は狩りに出かけて肉を持ち帰る。
しかし、大脳のエネルギーコストが再検討されると、この育児モデルへの疑問が浮上した。ヒトのエネルギーコストは男性による食糧供給によっても、肉を基本とした質の高い食事への切り替えによっても相殺できない。実は摂取カロリーの大半をまかなうのは女性たちが担う採集活動だった。研究では、娘の出産、子育てには祖母の方が男性よりずっと重要な役割を果たしていることが証明された。伝統的社会であれ、現代社会であれ、共同での子育てはそのほとんどが、近親の女性たちの間で行われている。つまり、一旦、受胎してしまえば、後の出産、子育てにおいて男性は余計な存在なのだ。
もし、男性が育児もせず、生活費も入れないなら、女性が1人の男性と感情的な絆を結ぶ必要などあるのか。ペアボンドが進化した残りの理由の中で、唯一残るのがボディガード仮説だ。
伝統的な狩猟採集社会では、ヒトは霊長類の基準からいくと不自然なほど大きなコミュニティをつくって住んでいる。通常、狩猟採集民のコミュニティは150人前後で構成され、数百平方マイルの範囲に3つか4つの狩猟採集グループが散らばっている。このグループのメンバーはゆっくりとだが着実に入れ替わる。50人ほどの狩猟採集グループには大抵、生殖年齢に達した男性が10〜12人ほどいる。男性としては、自分の留守中によその男が野営地に迷い込んでくるリスクは常にある。この問題は、女性側にとっても深刻だ。
ヒトのペアボンドが進化したのはおそらく、男性の数が非常に多い環境の中で生きる女性が、男性からの嫌がらせや子殺しのリスクから身を守るために、男性をボディガードとして確保したことから始まったのだろう。