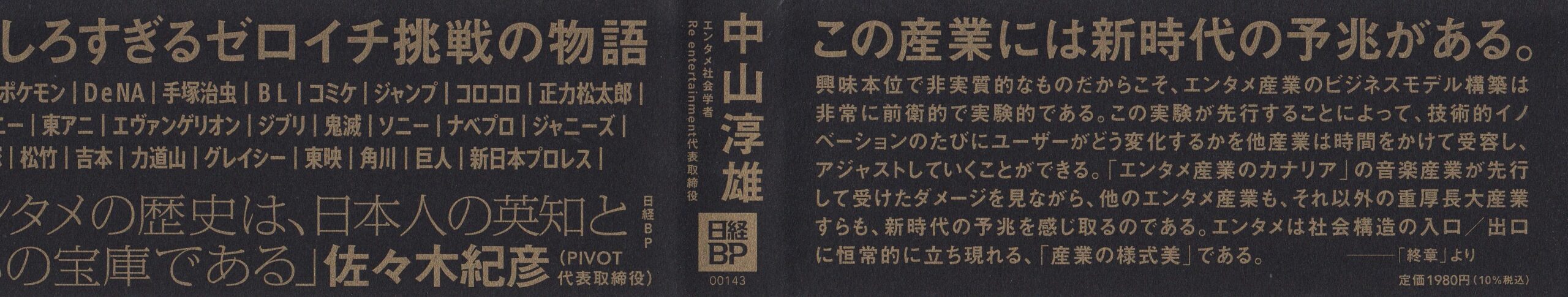エンタメ産業の構造
コンテンツは「媒介される情報(テキスト、音楽、映像、ゲーム)」でしかなく、本質的にはすべて1個人としてのクリエイターもしくはクリエイションを行うチームによって作られ、ユーザーに届け、楽しませるものである。大作映画だとしても、全世界に配信されるゲームだとしても、その発生源のクリエイターがまずありき。そしてメディアの先に受け取るユーザーがいる。作品を通じて、という間接の形式はとっていても、エンタメ産業は一種のコミュニケーション産業と言える。
エンタメの凄いところは、このクリエイターの偉業があまりに際立つおかげで、そこにIP(知的財産)と呼ばれる「権利」が発生することである。ブランドがIP化するおかげで、その本人やオリジナルのクリエイターが不在だとしても、あたかもそこに同じ世界が再現されているかのように、商品が「オーラ」をまとう。そして、その商品や体験への満足度がブランドとなっているからこそ、また新たに購入される。
クリエイターは時代に合わせてメディアを選ぶ。例えば映画館はかつて娯楽の代表として隆盛した。大正時代に既に100万部のミリオンセラーがあった書籍・雑誌、それを全国でも販売できるようにした書店流通の世界も同様だ。これらの「メディア」は媒介者でしかないが、コンテンツの力によってメディア自体にもブランドがついてくる。
テレビは、人類にとって最初に出会った「1億人が同時に同じものを見聞きするメディア」となり、その中でコンテンツとユーザーを奪い合ってきた。2010年代のユーチューブは様々な動画がとめどなくアップされるメディアとなった。2020年代には、TikTokで5秒10秒のコンテンツを見ているうちに、1時間くらい平気で時間をつぶせてしまうようになった。
クリエイターは、ユーザーがその時最も欲しているメディアを使って、自分自身がエンターテイメントだと思えるものを届けていく。
エンタメ産業のカナリア
音楽業界は、100年の歴史の中で何度もつぶれている。それも1年で市場の9割が吹き飛ぶような事態ばかりだ。なぜなら音楽というのはテクノロジーの変化を最前線で味わうからだ。「音楽を人に聴いてもらって対価をもらう」というビジネスモデルは、想像以上に脆弱である。音楽は誰でも作れるし、聴く人は日常的に無料で聴いている。
そこに市場を発生させるには、巧妙に構築された「仕組み」が必要である。「仕組み」はテクノロジーに支えられているが、それゆえ新しいテクノロジーが出現すると「仕組み」そのものが覆され、新しい市場を生み出していく。そして、音楽業界で発生した激震は、その後必ず出版や映像、ゲーム業界に派生していく。
そもそも「権利」という概念を獲得するまで、音楽は空気や自然のようなものだった。クラシック界きっての人気作曲家と言えばモーツァルトだが、彼があれほど多作でありながら常に貧しい生活を強いられたのは「曲の切り売り」によるものである。彼は依頼を受けて作曲するたびに、その曲を依頼主に譲渡していた。
19世紀になり「著作権」が確立し、「楽譜」と「印税」というビジネスモデルが確立したことで、音楽は市場として育ち、クリエイターは収入の確保を可能にした。
だが「権利」を確約するメディアは絶対的なものではない。音楽を一般の人も楽しむようになったのは、音楽専門誌が生まれ、ピアノによる演奏の普及があった19世紀である。それによって人々は楽譜を買う習慣を手に入れ、音楽出版社を通じて対価を作曲家に戻す仕組みが生まれた。ここで成長したのがピアノ市場である。
しかし蓄音機の発明による「レコード」の普及が、ピアノの市場を奪い取っていく。1914年にエジソン(現GE)、ビクター、コロンビアの大手3社を含む18社だったレコード会社は1918年には166社に激増し、1920年代はレコードが大量普及した。その結果、ピアノが売れなくなった。さらに安価になったラジオが急速に普及し、蓄音機の市場をかっさらう。
これと同じレベルの大転換が音楽の世界では繰り返されてきた。ラジオからテレビに、テレビからCDに、CDからネットに、という「メディアの乗り換え」のタイミングで、音楽市場には革命が起きてきた。
世界の音楽市場はユニバーサル、ソニー、ワーナーの3社で7割を占める。世界トップ3社は1970〜90年代を通じてM&Aを繰り返してきた。レコードからCD、iTunesのダウンロード配信、スポティファイのストリーミングと、技術革新に対抗するために「大きくなって交渉力をつけて、権利収益を最大化させる」ことに腐心してきた。
あらゆるコンテンツ産業の中でここまで技術革新と権利交渉が未来を決定づけてきたものは音楽の他には存在せず、それもこれも産業としての脆弱性を関係者が強く自覚しているがゆえの自己防衛でもある。