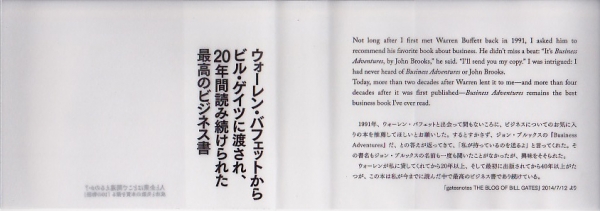ゼロックスの物語
複写機にはマーケティング上の問題が立ちはだかった。そもそも書類を大量に複写したいとは誰も思わなかった。ビジネスマンも弁護士も、書類の写しが5部必要なら事務員に5部写させていた。さらに「写す」という言葉には、偽造といった好ましくない語感がつきまとっていた。
20世紀になると、こうした見方は様変わりする。工業化の波によって複写の必要性が高まり、事務所類を複写する作業が急激に増えた。20世紀に入ると謄写版印刷も事務作業に欠かせないものとなった。
1930年代から40年代になると、謄写版よりはるかに高品質を誇るオフセット印刷機が事務用機器として広く採用された。ところが、オフセット印刷機も謄写版と同じく、コストがかかり、印刷部数が多い場合に限られた。安価で速いコピー機の開発は遅々として進まなかった。
困難な目標に向かって、必ず達成できると周囲を鼓舞すること
1950年代に入って、事務用コピー機が登場しはじめた。初期のコピー機には深刻な欠陥があった。湿った状態で紙が排出されるので、乾かすのに時間がかかり、さらにメーカーが提供する特殊な加工紙を使う必要があった。そこで、1950年代末、ゼログラフィ(乾式複写法)という新たな原理が登場した。ゼログラフィ・コピー機が発売された事で、アメリカ全体の年間コピー枚数は、50年代半ばには2000万枚だったのが、1966年には140億枚と飛躍的に増えた。
その偉大な技術革新を実現し、何十億枚ものコピーを生み出す装置を開発したのがゼロックス・コーポレーションだ。ゼロックスはコピー機の成功によって、1960年代にどんな企業よりも目覚ましい飛躍を遂げている。
ゼロックスの前身は写真印画紙のメーカーのハロイド・カンパニーである。第二次世界大戦直後に競争が激しくなり、人件費が重荷になると、ハロイドは新しい製品を開拓する必要に迫られた。そこで研究者が選択肢の1つとして注目したのが複写技術だった。開発費は莫大なものになった。1947年から60年にかけて、ハロイドがゼログラフィに投じた資金は約7500万ドルにのぼる。これは同期間の営業利益の実に2倍の額だ。会社はよほど先見の明のある投資家に頼るしかなかった。
1958年、ハロイドは社名をハロイド・ゼロックスに変更した。ゼロックスの物語には19世紀的とも言える古めかしい雰囲気が感じられる。粗末な実験室でこつこつと研究に勤しむ発明家、家族経営の小さな会社、開発初期段階でのつまづき、1つのアイデアに賭けた事業モデル、自由競争の正当性を証明する最終的な勝利。だが、それだけではゼロックスの全体像を理解した事にはならない。ゼロックスは株主、従業員、顧客に対してだけでなく、社会全体への責任を果たしたという意味で、19世紀の多くの企業とは対極にある。
「不可能と思うほど困難な目標に向かって、必ず達成できると周囲を鼓舞すること、これらはバランス・シート以上に重要だろう」と創業者の孫ウィルソンは語っている。ゼロックスは地元の教育機関への寄付だけでなく、利益に直結しない分野で果敢にリスクをとっている。「企業は社会の重要な問題について、立場を表明する事から逃げてはならない」。これはビジネスの世界では異端とみなされる発想だ。社会問題について立場を明らかにするという事は、反対の立場をとる顧客を遠ざける事になるからだ。
ゼロックスが明らかにしている社会的立場として、特に目立つのが国連への支持だが、様々な抗議が殺到するようになった。しかし、上層部は屈せず、やがて多方面から賞賛の声が寄せられた。ウィルソンは、理想を貫くことこそがビジネスで成功するための最良の道であると訴えている。