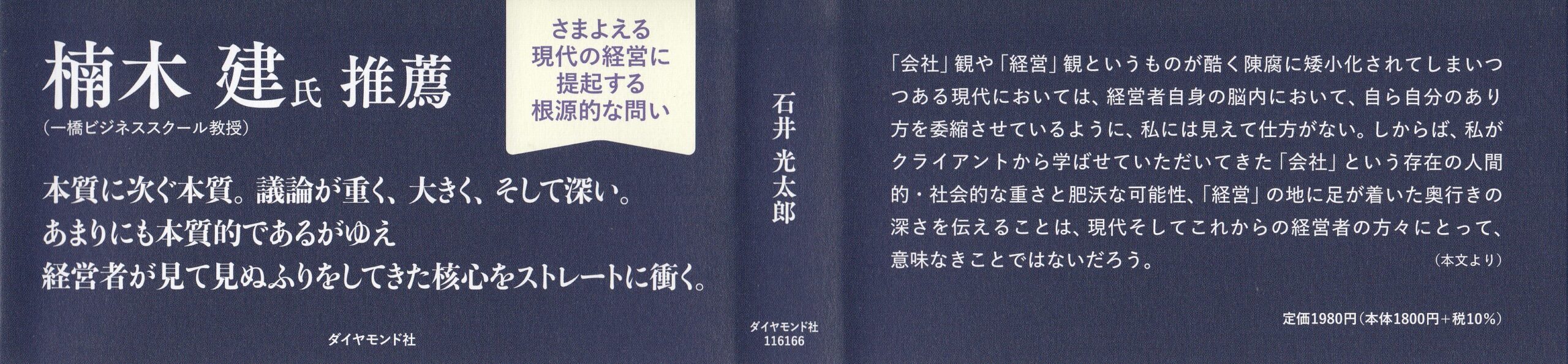競争戦略によって会社は目的を見失った
製品やサービスをもっと買ってもらうにはどうすればよいか、もっと良い製品やサービスに改良するにはどうすれば良いか、もっと安くするにはどうすればいいか、そのために仲間を増やすにはどうすればいいか、得意先を増やすにはどうすればいいか。必死で考え、失敗も繰り返し、それでも愛着と情熱を持って挫けずに挑戦し続けるうちに、いつしか自らの製品やサービスは世に認められるものとなり、「商売」は繁盛し、気がつけば「会社」は大きくなる。
その頃になって、コンサルタントはやってくる。「競争」や「経済性」という概念を説きながら、病巣を映し出すレントゲン写真やCT画像を撮り始め、撮像された姿から多くの問題点を指摘し、将来への懸念を表明する。
無意識のうちに、「商売」は「事業」、「会社」は「企業」という競争戦略論で概念化された存在として扱われる。そして「事業」の成否は、過去の経験や実践に基づいた勘ではなく、撮像された事実に基づく科学的・論理的な分析によって明らかにできるのだと宣託を下す。
軍事概念であった「戦略」をビジネスの世界に持ち込んだのは、コンサルタントの実に巧みな比喩であった。ビジネスを勝つか負けるかの一点で見る、というシンプルさは経営をする者の琴線に触れ、痛いところを突いていた。
そして、経営者はどうやってこのゲームに勝ち残るかは考えていても、なぜこのゲームを始めたのか、何のためにやっているのかには、いつしか無頓着になっていく。夢と志を持った人間の営為である「商売」や「会社」が、ただゲームの参加者へと矮小化され始める。
さらにコンサルタントは「競争に勝てなければ死ぬ、勝てなければやる意味もない」と存在を否定する。コンサルタントは、生きるための手段を、目的とすべき絶対的価値にそっとすり替え、それを刷り込むことに成功してきた。
レントゲン写真やCT画像が、生身の人間の姿でないのは自明すぎることである。それと同じくらいに、競争分析であぶり出される企業像は「会社」の姿そのものではないはずである。しかし、経営者たちは、それこそが自分たちの姿なのだと思い込まされてしまった。
会社が何を成し遂げるために生まれてきたかということよりも、なんでも良いから「勝てることをやる」ことこそ第一と考えなくてはならなくなってしまった。
今や、経営方針に掲げる事業分野の選別基準として、「利益率の高い事業」という尺度しか持たない「会社」さえ現れる始末である。そこにが概念としての「企業」はあっても、個性ある法人としての「会社」の匂いは全く嗅ぎ取ることができない。
「経営者」は「会社」の利益に奉仕する、交換可能な歯車となった。「経営者」の掌中からは、大切な何かが失われていくことになった。それが「経営」そのものであったのではないか。
原点に立ち返れば、「会社」とは競争をするために生まれてきたものではない。せいぜい言うとしても、込められた夢や志を体現するために、競争しなければならなくなった、というだけの話である。その逆ではない。「経営者」はもう一度、「経営」をその手に取り戻されなければならない。
法人格としての主観が大切である
かつては個々の経営者それぞれに秘められた「芸当」「奥義」であったものを、明るみに引っ張り出し、「会社を率いて導く」という日常的営為に「経営」という名詞を当てることで、それを抽象概念として取り出してしまった。本質を抽象化することは事態を観察する眼鏡としては有意義だったが、それは知らぬ間にプロトタイプのような一般的規範へと姿を変え、「あるべき論」が増殖し始めた。
経営理論や経営手法をいくら寄せ集めたところで、それが経営になることなどありはしない。会社の経営というものは、1社1社がそれぞれ異なる世界で、異なる挑戦をしているものである。あなたの人生と私の人生が違うくらいに、それは違う。そこに共通のやり方や手法、必勝のセオリーなどが、あるはずもない。
経営理論や経営手法を概念化・模型化する際に行われる単純化とは、所詮物事を一面から切り取ることを意味するので、客観的にモノを観る切り口とはなり得ても、実践の処方に直結するわけではない。
そもそも経営とは、可視化できないことだらけである。だからこそ、経営なのである。何が正しい経営判断であるかは、論理や計算で客観的に決まるのではなく、第一義的には、視座をどこに据えるかで主観的に決まるものである。
「会社」において、改めて問われているのは、自社が善い「会社」であるとはどういうことか、という問いそのものである。経営を考える出発点も、善い「会社」の自己定義でなければならない。それは一般的なあるべき論としてではなく、それぞれ「会社」ごとに目指す固有で独自の姿の自己定義であり、言い換えれば、具体的に何を為すためにその「会社」が生まれ、営みを続けているのかということである。その「価値」軸だけは、他人に預けてはいけない。