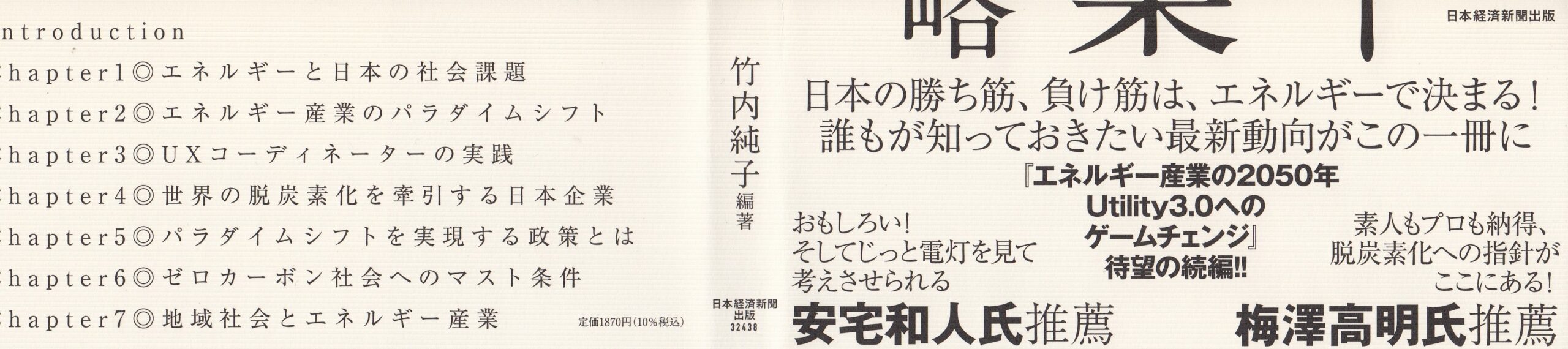脱炭素への課題
気候変動問題はエネルギー産業に大きな、そして急速な変化を求めている。2020年10月、日本政府は2050年までに、温室効果ガスの排出を実質ゼロにする、すなわち「2050年カーボンニュートラルを目指す」という方針を示した。しかし、実現に向けたハードルは相当高く、政府は具体的な道筋を示せずにいる。
エネルギーの脱炭素化に関しては、再エネ電源をいかに導入するかといった電力部門の「発電の脱炭素化」の議論に偏りがちだが、電力が最終エネルギー消費に占める割合(電化率)は約30%に過ぎない。残る70%は工場のボイラーや輸送部門の内燃機関などエネルギー消費の最終段階で、化石燃料を直接燃焼させている。この70%を放置したままでは、CO2排出量の大幅な削減はできない。したがってこの「需要の電化」と「発電の脱炭素化」を両輪で進める必要がある。
「需要の電化」が進展すれば、人口減少と省エネ化が進む中でも電力需要は増加していく。つまり、CO2フリーの電気の需要が大量に生じることになる。エネルギー産業は、この需要に対して、安全性を確保した上で、自給率、経済効率性、環境適合に配慮しつつ、いかに応えていくかが課題になる。
CO2フリーの発電技術には、太陽光発電、風力発電、原子力発電、水力発電、水素火力発電などが挙げられる。各技術を最適に組み合わせて、増大する電力需要に応えなければならない。
ところが、太陽光発電や風力発電などの自然変動電源と蓄電池の組み合わせだけでは、再エネと蓄電池を増やせば増やすほど、その稼働率が減少してコスト高となることが避けられない。一方、水素火力発電を調整用電源として組み合わせれば大きくコストを下げる可能性もあるが、水素火力発電には、燃料である水素をどのように調達するかという課題がある。
2020年時点で、世界で製造されている水素の内約95%がグレー水素である。これは、化石燃料を蒸気メタン改質や自動熱分解と呼ばれる手法で水素と二酸化炭素に分解することで得られる水素である。製造過程でCO2が発生する。したがって、CO2排出量をゼロにするには、製造過程でCO2を排出しないブルー水素、グリーン水素に置き換えていく必要もある。
ゼロカーボンという目標は需要側にも大きな変化を求める。しかしながら、鉄鋼業や化学産業は製造プロセスにおいて原材料として化石燃料を用いているため、排出するCO2をゼロにすることは極めて困難である。カーボンニュートラルを掲げる多くの国では、この目標の達成は非連続の変化の先に初めて可能になるとみなされている。
エネルギー産業のパラダイムシフト
脱炭素の時代への移行は、炭化水素を輸入に頼る日本にとって、実は大きなチャンスとなる可能性がある。だからこそ「需要の電化」と「発電の脱炭素化」を進め、強靭なエネルギー需給構造を作ることが重要である。水素輸入については、日本がカモネギにならないように、国際水素貿易をコントロールするべく、国際貿易分野に関する技術開発や制度設計におけるリーダーシップが大きなカギを握る。
現在、運輸部門のCO2排出量は世界全体の16%を占めているが、クルマは最大の変革期を迎えており、その鍵は「CASE」だと言われている。
C(Connected):コネクテッド
A(Autonomous):自動運転
S(Shared/Service):シェアリングサービス
E(Electric):電動化
エネルギーシステムの観点から捉えるとCASE化のインパクトは非常に大きく、クルマは化石燃料を消費する存在から、搭載するバッテリーを使って脱炭素化されたエネルギーシステムを支える存在へと変容していく可能性を秘めている。
まずは主力電源として大量導入が進む太陽光発電や風力発電など、発電出力が天気次第で変動してしまう再生可能エネルギーの変動を電気自動車(EV)のバッテリーで調整することで、その調整コストを大幅に下げる役割が期待される。
EVの比率を増やせば、再エネの導入が加速し、電力部門のCO2も削減され、再エネを増やすことで運輸部門のCO2排出を減らすことができる。さらにCASE化が進めば、1人あたりのクルマの所有台数も減り、結果として素材部門におけるCO2削減効果も期待できる。
CASEとなったクルマは、移動可能な分散型電源としての側面を持つ。住居や事務所が災害など何かしらの原因で配電網から孤立しても、そこにEVが1台あれば当座の電力は確保できる。2030年には一世帯の使用量の1週間程度の電気を蓄えられるようになる。
CASEはクルマ以外のデバイスでも想定される。あらゆるCASE化が、日本政府が目指すSociety5.0の1つの目標地点であり、それによるエネルギー利用や産業構造の変容は、カーボンニュートラルに向けた大きな力になる。