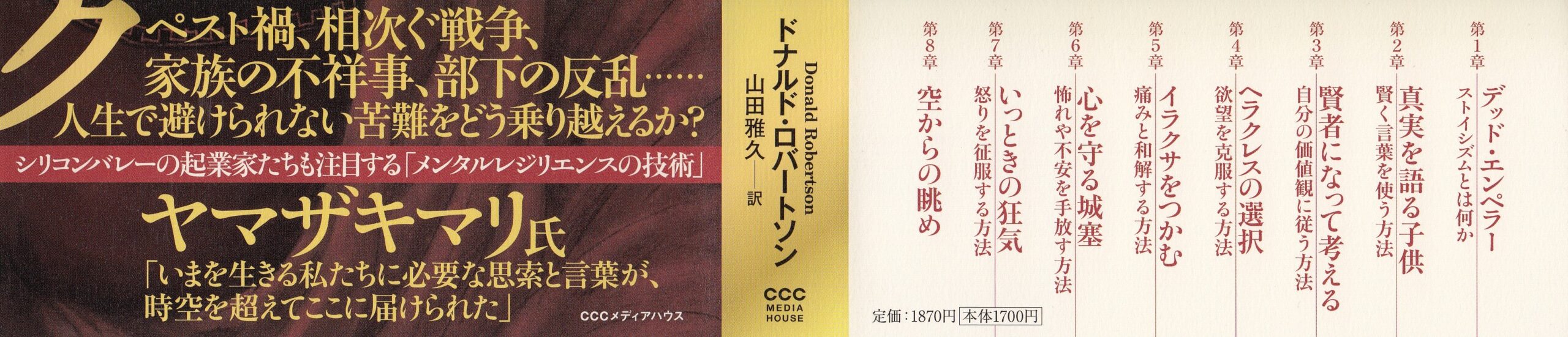生を見直すストア哲学
ストア哲学は、人生の目的をどう見つけるか、逆境にどう立ち向かうか、怒りをどう克服するか、欲望をどう和らげるか、苦痛や病気にどう耐えるか、不安に直面した時にどう勇気を示すか、喪失にどう向き合うか、平静を保ちながら死を迎えるにはどうすればいいかを教えてくれる。
マルクス・アウレリウスは、ローマ帝国の皇帝として、たくさんの困難に立ち向かった。『自省録』は、彼が自分を導いていった方法を知ることができる。
マルクスが幼い頃から学んできたストア哲学は、自分の死を穏やかに、そして理性的に受け入れるための訓練でもあった。ストア派にとって、死について学ぶことは人生の奴隷にならない方法を学ぶことでもあった。
避けようが自分の死から目を背けなければ、いつまでも生きていられそうな幻想に迷い込むことはない。また、避けられないのであれば、その不幸を心配する必要もなくなる。人生において死は最も確実なものであり、知恵ある人にとって、最も恐れなくてもいいものの1つになる。永遠に続くものは何1つなく、いつかはすべてが過ぎ去っていく。
その真実に抗おうとすれば、そこに残るのは、自分の力が及ばないものをコントロールしようとしている自分だけになる。そのことが理解できれば、「今」の大切さに目を向ける有益につながっていく。これが、死を受け入れることで、その都度、生を見直すストア哲学の訓練法になっていった。
マルクスは20代半ばでストア派として生きる決意をしている。それ以来、人としても統治者としても、ストア哲学が説く理想に近い人物に自分をつくり変えるトレーニングを続けてきた。
ストア哲学の核となる教え
ソクラテス以後のヘレニズム哲学が明らかにしようとしたのは、「どう生きたら人は幸せになれるか」ということだった。そして、各学派は、人生の指針をどう定義するかによって区別できる。ストア派にとっての指針は「自然と調和して生きる」ことにあった。それは、私たちの内なる自然を、宇宙の自然に調和させることを意味している。
ストア哲学が重視したのは理性だった。人間は他の動物と多くの本能を共有し、動物と同じように衝動によって動かされている。しかし、一方で人間は「考える生き物」でもあり、理性を働かせることでその衝動に従わないこともできる。このように理性的に考える能力こそが、私たちを人間たらしめている。
私たちの意思決定を司どる理性を、ストア派は「精神を支配する力」と呼んだ。この「精神を支配する力」を使うことで、心に浮かんだ思考や感情、衝動を評価し、それが善いものか悪いものか、健全なものか不健全なものかを判断している。
そのため、理性を正しく働かせる必要がある。それを可能とするのが、人に元々備わっている知恵である。知恵を用いて理性を正しく働かせる、そうすることが内なる自然と宇宙の自然を調和させ、豊かな人生を送ることにつながるとストア派は考えた。
ストア派にとって、知恵を愛することと徳に基づいて行動することは同じ意味を持っている。ストア哲学の徳には、知恵、正義、勇気、節制の4つの美徳がある。ある行動において知恵を使うには、善、悪、善や悪とは無関係な善悪無差別の違いを理解し、選択を誤らないようにする必要がある。そして、美徳(知恵、正義、勇気、節制)を選択すれば善につながり、悪徳(無思慮、不正、臆病、不節制)を選択すれば悪につながる。それ以外のお金や名誉などすべては、善悪無差別であり、そこに大きな価値は置かない。ここでいう善と悪は、道徳的な意味での善悪ではなく、幸福を追求する上で善い(有益な)ものであるか悪いものであるかを指している。
つまり、ストア派は、お金や名誉といった外的なものにもある程度の価値はあるが、私たちの心を捧げるほどの価値はないとした。ストア派にとって何より大切なのは徳である。そのため、富などの「好ましいもの」を追求するために徳を犠牲にすることはありえない。
自分の感情を客観的に捉える
ストア哲学が教えているのは、無意識的に起こる閃光のような最初の反応を善いも悪いもなく受け入れることである。大切なのは、どう感じるかではなく、生じた感情に対してどう反応するかである。ストア派は、ある出来事がすべての人に同じように見えるわけではないこと、つまり、今の自分の視点が多くの内の1つに過ぎないことを理解するために認知距離を取る訓練を行った。
マルクスは、私たちの意見を、物体を照らす太陽の光に例えている。自分が下した価値判断が現実に投影することがわかれば、外部で起こっている出来事からその価値判断を切り離すことができる。そして、それを客観的に表現する言葉の用い方を受け入れてきた。
どのような状況にあっても、このスタイルで現実を表現することが、ストア哲学を実践する上での基本になる。