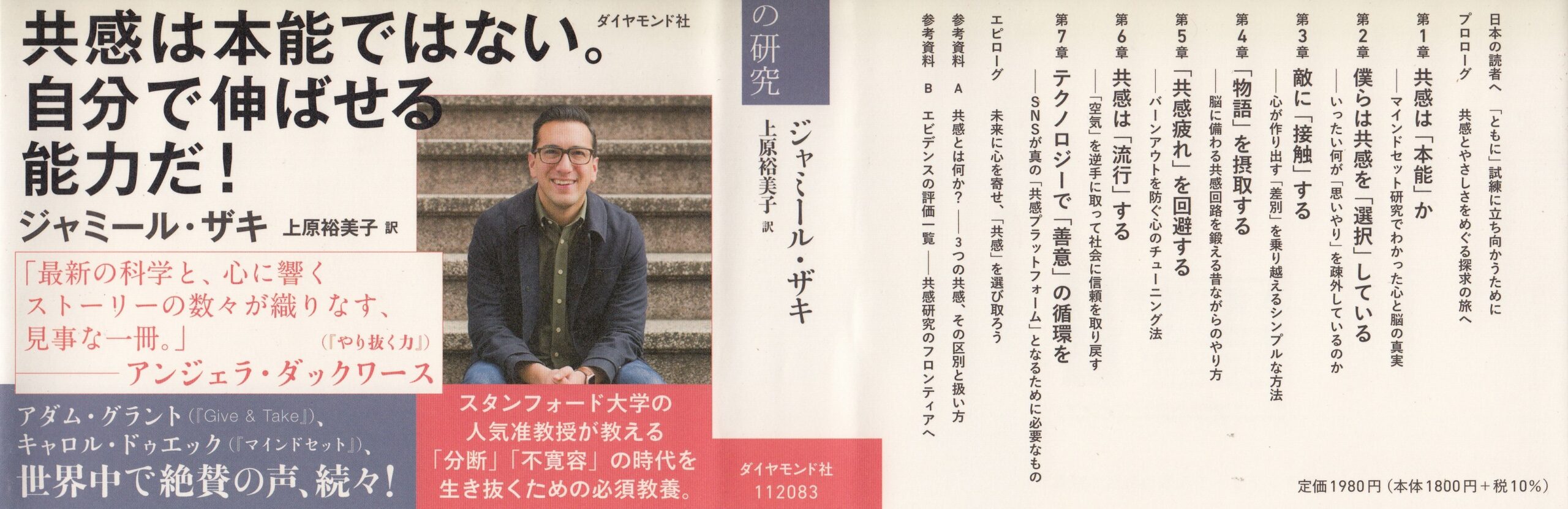共感の本能
共感を通じて、私たちは互いの世界に近寄り、相手の気持ちを推測する。何度も何度も、信じられない回数、私たちは実際にこの作業を正しく実行している。赤の他人が語る感動的な話を聞けば、その人が感じている気持ちをかなり正確に描写できる。相手の顔を見ただけで、その人が何を面白がっているのか察したり、その人が信用できそうかどうか直感的に判断したりする。
しかし、共感の最も重要な役割は他にある。やさしい行動、親切な行動を引き出すことだ。自分を犠牲にしてでも他人を助けようという気にさせる。生き物は他の生き物の痛みを見て、その痛みを自分も感じる。だから、自分を助けるために、相手を助けようとする。
共感すると、相手にやさしくする。この法則は人類が生まれる前から存在している。野生のネズミも、ゾウもサルもカラスも、共感と親切、その両方を示すことがわかっている。人類ではこうした共感の形が飛躍的に進化した。だから現代の私たちは、友達やご近所だけでなく、敵、他人、そして映画や小説に出てくる架空の人物の頭の中にも入り込むことができる。
そもそも共感の本能は、視界に入る他人のほとんどが「身内」という時代に進化し確立したものだ。かつては、友人もご近所も、だいたい似た人間ばかりだった。お互いを理解し合うチャンスも無数にあった。
しかし、時代が進み世界が発展するうちに、やさしさの行使は難しくなっていく。都市が広がり、多くの人間が小さな世帯単位で生活することで、視界に入る人間の数は増え、その中で「知っている人」の割合は小さくなった。教会の礼拝、チームスポーツへの参加、食料品店でのショッピングなど、人と人が定期的に接点を持つ儀式は、もっぱら単独行動へ、しかも多くの場合はインターネット越しの活用へと置き換わった。
共感力は伸ばすことができる
共感力は、少なくともある程度は、遺伝的なものだ。研究によれば、共感力の約30%は遺伝で決定していることがわかった。寛容な性格かどうかも、ほぼ60%が遺伝で決まる。IQの遺伝的要素は大体60%なので、それと肩を並べる。この度合いは変動しない。
しかし、人間の脳と精神は生涯を通じて変わり続けるという「こころ移動説」では、それでも人は大きく変われると考える。体験、環境、習慣などが共感ややさしさに大きく影響してくる。共感力が経験によって形成されることは、数十年にわたる様々な研究で確認されている。
大人になってからも、環境や状況によって共感の位置が固まってしまうことがある。うつを経験すると、その後の数年間、共感力が低くなりやすい。うつ以外でも、過酷な体験の影響は、多様な形で現れる。
私たちは偶発的な出来事、経験によって共感力を変化させるが、共感力を意図的に伸ばすことも可能である。「共感力は伸ばせる」と信じるだけで、実際にそうなる。こうしたマインドセットは本人の行動に影響する。マインドセットを変えるのは第一歩となる。
物語の力は共感力を高める
「こころ移動説」では、思考回路は筋肉だと考える。運動で筋肉を鍛えられるのと同じで、適切な練習をすれば、知能を伸ばしたり、性格を変えたりすることができる。重要なのは、共感力「高」の方へ一時的に寄せるのではなく、その位置にとどまれるようにすることだ。心理的転換を起こすためには、日常的かつ反復的な体験が必要だ。
共感するというのは心を相手の方へ、つまり自分の現実ではない対象へと寄せることだ。ただぼんやりするだけで今の現実ではないことを考え始める脳の放流機能がしっかり働いていると、より深く相手の心に入り込み、より正確に考えや気持ちを理解することができる。対象が実在する人物でなくても同じことは起きる。
大昔の人は、物語の力を使って、他人の人生を想像し、起こりうる未来に向けて計画を立て、文化として守るべき規範を共有した。物語は共感を阻む障害物を乗り越える力にもなる。物語を通して、私たちは他人との距離感を縮め、人を思いやることのハードルを下げることができる。
実験によると、熱心な読書家は、読書量の少ない人と比べて、他人の気持ちを理解するのが得意だ。お話をたくさん読んでいる子供は、本嫌いの同年代と比べて、人の心を察する力が早く伸びる。特に文学や芝居のようなナラティブ形式の芸術は、他者の心について想像をめぐらすきっかけになる。