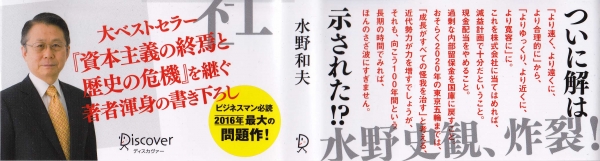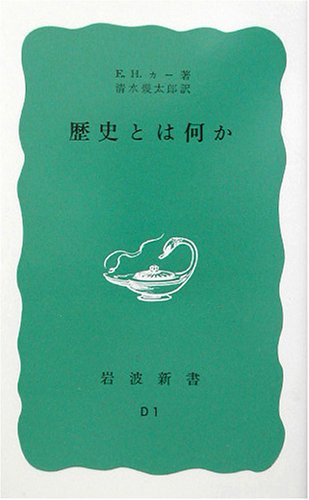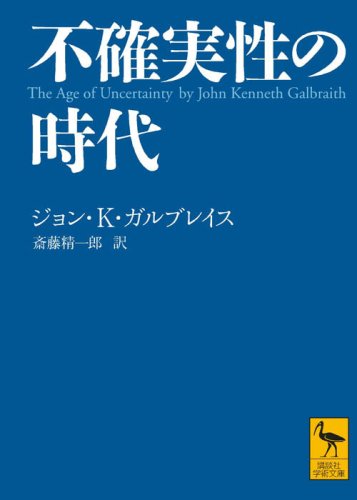資本帝国の繁栄
20世紀までの株価は利子率と連動していた。株価は企業業績を反映し、付加価値を分配面からみれば、株価が上昇する時は好況で、雇用者報酬も増加した。1997年までは雇用者報酬は不況でも減少することはなく増加基調にあったので、貯蓄が可能だった。貯蓄の増減は利子率によって決まっていたので、株価と利子率は同じ方向に動いていた。
ところが、20世紀末になると、新自由主義が世界を席巻し、国家は国民に離縁状を叩きつけ、資本と再婚することを選んだ。「資本帝国」においては、雇用者所得を減少させることで株高を維持し、資本の自己増殖に励むことになる。企業の自己資本利益率は、2001年度をボトムに上昇傾向に転じたのに対して、家計の純資産蓄積率は一層低下傾向を強めていった。
株価は過去最高益を更新中の大企業の収益性改善を反映して値上がりする一方、利子率は工場や店舗など過剰資産を反映して、マイナスに転じた。21世紀になると、資本家が、ヒト、モノ、カネを国境を自由に超えて移せる手段を手にしたことで、株価は世界の企業利益を映す鏡となり、利子率は国境で分断された国民の所得を映すようになった。
株高政策は資本家のためにしかならない
20世紀末までの金利と株価は、同じ国民国家の「景気」を反映して動いていた。しかし、21世紀になると、それぞれの見る対象が違ってきた。株価が見ているのは20世紀末に誕生した「電子・金融空間」をホームグラウンドとする資本帝国に君臨する「資本」。利子率が見ているのは近代の「地理的・物的空間」に立脚する国民国家の「経済」である。
そして、安倍政権が重視しているのは株価である。株価を重視する場合には、トリクルダウン理論「富める者が富めば、貧しい者にも自然に富が滴り落ちる」が成立していることが前提である。しかし、20年近くにわたって一人当たり賃金は減少しており、世帯の金融資産は減っている。即ち、トリクルダウンは生じていない。円安・株高政策を採用するアベノミクスは「資本帝国」の政策なのである。
株価が高値をつける一方、利子率はあくまで実物投資の収益率を反映しているため、「地理的・物的空間」の膨張がなくなれば、ゼロ金利になる。つまり、現在のマイナス金利は近代の終わりの象徴である。
成長の限界
株式会社は「無限空間」を前提として初めて利益極大化が可能である。しかし、IT革命とアフリカまで到達しようとしているグローバリゼーションで、21世紀は「閉じた地球」となった。「無限」空間を前提にした近代が「有限」空間に直面すると、成長自体が収縮を生むようになる。ドイツや日本の自動車産業の燃費競争における不正や日本の家電産業の不正会計がその表れである。
もはや「地理的・物的空間」には「より速く、より遠く、より合理的に」を実現する場所はなくなった。そこで作り出されたのが「電子・金融空間」だったが、これはバブルの生成と崩壊を生み出す。1980年代から現在までの36年間でバブル崩壊は11回となり、バブルは3年に1度生じては弾ける時代となり、「地理的・物的空間」にも大きな損失を及ぼし、資産をなくす無産階級を大量に生み出すことになった。
経済成長を目指す必要はない
今なすべきことは、21世紀はどんな時代かをまず立ち止まって考えることである。21世紀は「より速く、より遠く、より合理的に」を追求する「技術の時代」ではない。
今の日本は、資本係数は世界最大、自然利子率はゼロである。資本が過剰に積み上がって、コンビニエンスな社会、即ち、いつどこでも欲しいモノ・サービスが手に入る社会を築いた訳であり、無理な成長を目指す必要はない。「地理的・物的空間」が消滅して、成長メカニズムが崩壊した訳だから、成長を目標にすればその反動の方が大きくなる。