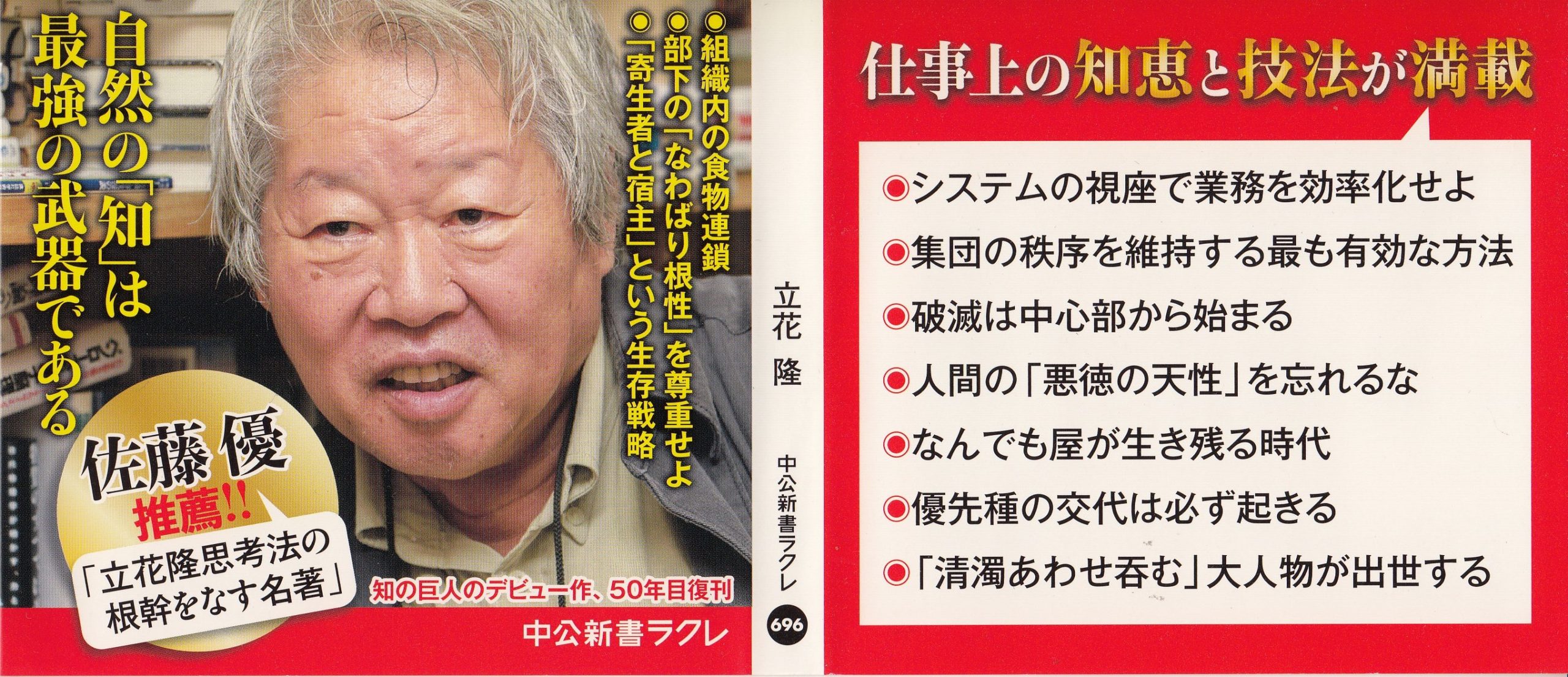部分最適ではなく全体を見よ
人類は進歩と繁栄を謳歌しながら、滅亡の淵に向かって行進しつつある。もし望みがあるとして、その望みの唯一の手がかりは、人類がこれまで金科玉条としてきた思考様式の変革にある。つまり、生態学的に考えるようになることである。この価値体系の転換なしに、人類の未来はない。
生態学(エコロジー)は、生物学の一分野で「生物と環境および共に生活するものとの関係を論ずる科学」である。生態学が研究対象とするのは、生物と生物の間の関係、さらには生物と無生物、つまり物質界との関係、あるいは環境一般との関係も含む。一言で言えば、関係の学問と言えるかもしれない。生物学的思考とは、正しい関係づけの上にたつ思考ということでもある。
全体は部分から構成されているに違いないが、部分において真であることが、必ずしも全体において真であるとは限らない。また、部分のすべてを知ったとしても、全体を知ったことにはならない。
科学は自然を対象とする。しかし、それぞれに自然の極めて狭い一部しか対象にしない。その中で、生態学は、あくまでも全体を対象にしようとする。対象を狭く限定すればするほど、科学は精密になることができる。反対に全体を問題にしようと思えば、あまりにも複雑でつかみがたくなってくる。
科学は、経験の集積である。しかしそれは、精密化を心がけるあまり、一面的で局部的な経験だけを取り上げて、そこから知識を抽出してくる。これに対して生態学の知恵は、経験全体からにじみ出してくるような知恵である。知識が優位に立つべきか、知恵が優位に立つべきかは、論を待つまでもない。部分において正しいことが、全体の中で正しいとは限らないからである。
技術が自然全体を壊す恐れがある
生態学の教える第一の知恵は、自然全体が1つの有機的なシステムになっていることの確認である。自然は単純なシステムではなく、複合システムになっている。自然全体の複合システムをトータルシステムとすれば、個別科学が探求するのはサブシステムである。
人間の文明は、知り得たサブシステムを技術によって改良することによって成立してきた。しかし、サブシステム内では有効に働く技術が、しばしばトータルシステムの中では弊害をもたらす。穀物増産のために用いられた農薬が、人体に吸収されて健康を害したり、あるいは害虫のみならず、他の小生物を皆殺しにした結果、生態系のバランスが壊れて、逆に害虫の大発生をみたりということが起きている。
例えば、プラスチックは、可塑性、不燃性、弾性、耐酸性などに優れ、工業生産システムの中では便利な材料である。しかし、プラスチックは一様に腐らないという特性も持っている。この特性のため、プラスチックは自然というトータルシステムの中で、捨てても自然の中で分解されずにいつまでも残る。これを燃やせば、有害ガスを放出する。サブシステムの下手な改良はトータルシステムを破壊してしまう恐れがある。
人工システムを再調整せよ
システムには閉鎖システムと開放システムの2種類がある。開放システムの中に入ってくるものをインプット、外に出ていくものをアウトプットという。いかなるシステムにおいても、インプットより大きなアウトプットを取り出すことはできない。これが自然の大原則である。自然の根底にある法則は、エネルギー保存則・質量不変則である。自然はどこかでちゃんと帳尻を合わせている。
開放システムのインプットとアウトプットが等しいということは、開放システムが終局的なトータルシステムではあり得ないということだ。インプットの起源をたどれば、必ずその開放システムを包含するより巨大なシステムにたどり着く。人間はこれまで、社会のシステムに自然をその一環として取り入れて考えることをしなかった。どんな社会システムも、自然というファクターに着目すれば、必ず地球システムに対して開かれている。
システムの管理において、大切なことは、開放システムの場合、インプットとアウトプットをうまく調節して赤字にならないようにすることである。閉鎖システムでは、その構造上サイクルを描いているが、サイクルをうまく回転し続けるようにしなければならない。
人間は、自然が無限であるという誤解をし、自然のシステムを破壊してきた。生態学から学ぶべきことは、人間活動全体を自然のサブシステムとしてうまく機能するように、再調整してやることである。