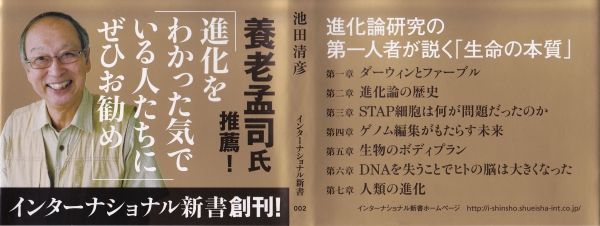進化にはいまだ謎が残されている
進化とは「生物が世代を継続して変化していくこと」である。従って、もし1つの個体が新しい能力を獲得したとしても、その性質が子や孫といった次の世代の個体に伝わっていかなければ、それは進化とは呼べない。
ダーウィンは人類に進化という概念を示した人物である。しかし現在主流になっている進化論の学説は、ダーウィンが提唱したものとは少し異なっている。現在の進化生物学の標準理論と考えられているのは、ダーウィンの自然選択説と、グレゴール・ヨハン・メンデルの遺伝学説を中心に、いくつかのアイデアを融合させた学説で、これは「ネオ・ダーウィニズム」と呼ばれている。その中核をなす考えは「偶然起こる遺伝子の突然変異が、自然選択によって集団の中に浸透していくことで、生物は進化していく」というものである。
進化という概念は「小進化」と「大進化」の2つに大きく分けられる。小進化というのは、種の枠組みの中で起こる小さな変化である。一方、大進化は種の枠を超えるような、大きな変化のことを言う。そして、小進化の方は遺伝子の変異と自然選択によって概ね説明することができるが、大進化の場合は単純に行かない。
遺伝子そのものだけでは大きな進化は生まれない
実のところダーウィニズムは、種の枠組みを超えるような大進化がどうして起こるのかを解明できていない。「突然変異」と「自然選択」で、遺伝子にどれほどの変異が起こったとしても、大進化が起きるという保証はない。ネオダーウィニズムは、遺伝子の変異だけで進化の仕組みを理解しようとした。しかし、多細胞生物の進化を解き明かすには、発生学の知識が必要である。単細胞生物は1つの細胞自体で完結しており、ある時点での遺伝子の発現パターンは一通りだけ。それに対し、多細胞生物はそれぞれの細胞で役割分担が決まっていて、細胞の種類によって遺伝子の発現パターンが異なる。
なぜ遺伝子が同じなのに、異なった細胞に分化していくのか、その理由は「それぞれの細胞ごとに、発現する遺伝子が違ってくる」からである。発現する遺伝子が異なると、つくられるタンパク質も細胞ごとに変わってくる。その発現する遺伝子の違いによって、皮膚細胞、肝細胞、神経細胞のように、別の細胞に分化していく。
遺伝子の発現パターンを制御するシステムが鍵
ネオダーウィニズムは「突然変異と自然選択によって、生物の形が世代を継続して変化する」と主張する。そうなると当然、形を作る遺伝子というものが存在しなくてはならない。しかし、これまで積み重ねられた知見によると、遺伝子はタンパク質をいつ、どこで、どれだけ作るかを決定するものであって、生物の形を直接的に規定するものではない。形に関しては基本的に、ほとんどすべての生物で同じような遺伝子が働いていることがわかってきた。
生物の個体の様々な形質と遺伝子は、直接的にはほとんど1対1で対応していない。同じ遺伝子を持っているからといって、必ずしも形質が同じになるとは限らない。生物の進化は遺伝子だけでは説明できない。同じ遺伝子が発現する場合でも、細胞内部や周囲の環境によって発動する機能に変化が生じてくるからである。遺伝子は外部の環境によって発現パターンに変化が生じる。この発現パターンが子孫に遺伝することが、進化へとつながるのである。
DNAの塩基配列に変化が起こらずに遺伝子の発現を制御するシステムのことを「エピジェネティクス」と言う。通常、遺伝形質の発現はDNAに記録されている遺伝情報に起因するが、エピジェネティクスは塩基配列を変えることなく、遺伝子の発現を変化させ、その結果表現型も変わる。さらに、エピジェネティクスによって制御された状態は、場合によっては遺伝する。このような「DNAに書かれていないシステムが世代間で引き継がれ、さらに固定化する」ことが進化の原因の1つではないか。