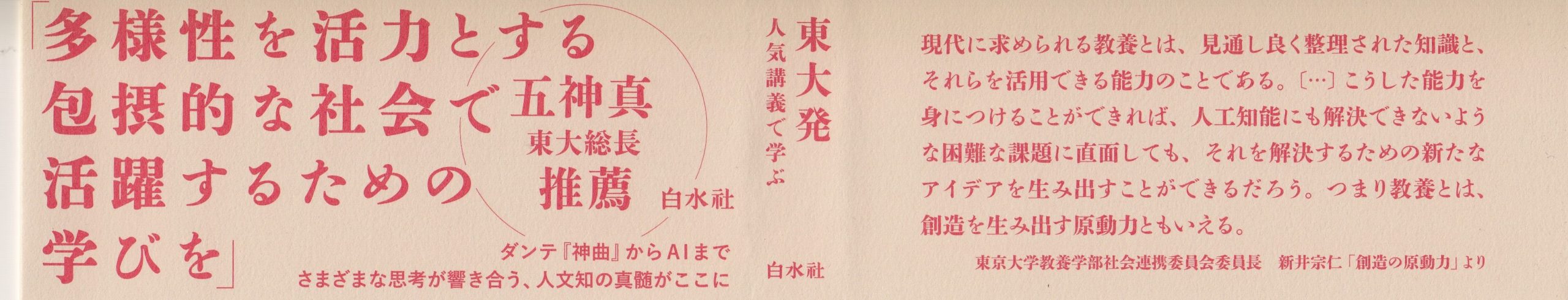原発の最終廃棄物と日本社会
原子力発電所で電気を発電した後に発生する「使用済み核燃料」からリサイクルできるものを取り除いた残りが「原発の最終廃棄物」である。正確には「高レベル放射性廃棄物」という。これは1970年前後から日本が原発を使用してきた結果、蓄積されてきていて、どこかで処分する必要がある。
これは処分しなければならないという点で、原発の推進派と反対派という立場を越えた議論ができる可能性がある問題だが、そうはなっていない。ここに日本社会のあり方や難しさが現れている。
高レベル放射性廃棄物には40種類以上の元素が含まれる。その中には、半減期が百万年を越すようなものも含まれている。したがって全体として強い放射能を持っており、それが長く持続する。十万年ほど経過すると元々の天然ウラン鉱石と同じ程度の弱い放射能になってくる。そこで一万年から十万年程度の間、安全性を確保することが、原子力業界としての目標とされている。
十万年もの間の安全を確保するために、この高レベル放射性廃棄物をどのように処分すればいいのか。現在では地下深く埋めてしまう「地層処分」が標準的な考え方となっている。その基本的な考え方は「十万年の安全を確保するためには、人の手を離れても安全性が保たれるようにする必要がある」というものだ。そのために、地下300m以深の安定した地層に埋設してしまう。坑道も埋め戻して、そこに人が辿り着けないようにしてしまう。埋める時は、放射性物質が環境中に出てこないように、ガラスと混ぜて固め、厚さ20cmの鋼鉄製の容器に入れ、周囲70cm程度を粘土で固める。これらを30〜40年かけて地下に埋めていく。費用は約3.8兆円と見積もられているが、費用が増大する可能性はある。この費用は既に、日々の電気料金の中から積み立てられ始めている。
専門家は定量的な判断を積み重ねて「大丈夫だろう」と考えているが、一般の人々は「万が一」を考えずにはおられない。少なくとも現状で国民の多くがこの問題を知り、地層処分に対して概ね合意ができているとは考えられない。しかし、日本では既に地層処分を行うことが法律で決まっている。
使用済み核燃料から高レベル放射性廃棄物を取り出すための「再処理」のための工場は、国内では青森県に置かれている。工場自体は未完成だが、そこには全国の原発から使用済み核燃料が集まってきている。各原発のサイト内には使用済み核燃料を保管するプールがあるが、それらはかなり一杯になってきている。青森の再処理工場のような「使用済み核燃料を運び出す先」がなくなると、原発は運転できなくなってしまう。
一方、青森県行政は「再処理工場はあくまで中間的な施設であって、青森県は最終処分地ではない」ということを当初から強調してきた。
「どこで処分するか」という各論になると、想定されるのは常に人口の少ない地方の過疎地だ。地方の側では「原発の電気を使っているのは主に都会の人間であるのに、どうして自分たちがリスクを背負わなければならないのか」という気持ちが生じる。社会学ではこのような状況を「受益圏と受苦圏の分離」と呼んできた。利益を受ける地域と、リスクを受け入れる地域が分離していることが問題の本質にあるという見方だ。
この問題の責任は、第一義的には処分方法や処分地を明確にしないまま原発を推進してきた政府や電力会社、あるいは原子力の専門家にある。しかし、この資本主義社会において廃棄物などの後始末をよく考えずに技術を使い始めるのは常態でもある。原発利用がスタートした戦後すぐの時代においてはなおさらだ。であるとすれば、原子力業界にお任せで電気を用いた生活を享受してきた国民の大多数にも、責任の一端がないとは言えない。
国民の一人ひとりがこのような問題を知ったからといって、急に何かが解決するわけではない。しかし、より多くの一人ひとりがこのような問題を知ることなしに、問題がより良い方に動いていくことはないのではないか。そして、それ以上に、自分の生きる社会の抱える問題をより深く知ることは価値のあることである。