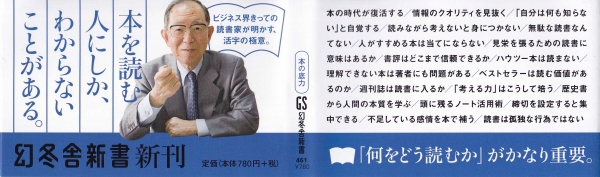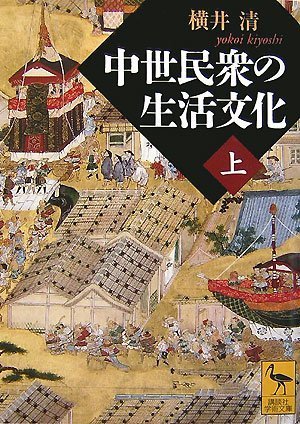読書は自由な世界を与えてくれる
「本なんて役に立たないから、読む必要はない」という考え方をする人が少なからず出てきたということは、小さい頃から遊びも勉強も習いごとも、親や周りから、よかれと思って与えられた環境で育った人が多いことを表している。
与えられたものの中でばかり生きていると、「自分の頭で考える」ということができなくなる。自立した思考ができないから、たまたま与えられた狭い世界の中だけで解決してしまう。
周りから与えられた狭い世界の中で、何に対してもすぐに実利的な結果を求める。そんな生き方は、精神的に不自由である。今の社会はかつてないほど自由度の高い環境だが、「何でもあり」の世界は、自分の軸がなければ、実はとても不自由である。それは前へ進むための羅針盤や地図がないのと同じだからである。それらがなければ、限られた狭い中でしか動けない。自分の軸を持つには、本当の「知」を鍛えるしかない。読書はそんな力をもたらしてくれる。
本の時代が復活する
本がかつてほど売れなくなったのは、明らかにネットの普及にある。しかし、この流れはそのまま続かず、再び本が見直される時代がくると見ている。
今は情報拡散力の高いネット上のソーシャルメディアによって、あっという間に世界中に情報が伝達していく時代である。ところが、その情報に対する信頼度は低い。1つ1つの情報が、どこの誰が責任を持って発しているのかが見えないがゆえに、いい加減な情報で溢れかえってしまう。誰が発信しているのかは、とても重要なことである。その点、ネットと比べて、本は発信する人が誰なのかがはっきりとわかる。極端な意見であっても、読み手はこの人が責任を持って書いているんだなと安心して読み進められる。
知識を得るには「考える」ことが必要
同じことでも、本を通して知ることと、ネットを通して知ることとは違う。ネットで検索すれば、簡単に知ることはできる。しかし、そこで得られるものは単なる情報にすぎない。細切れの断片的な情報をたくさん持っていても、それは知識とは呼べない。なぜなら情報は「考える」作業を経ないと、知識にならないからである。考えることによって、様々な情報が有機的に結合し、知識になる。読書で得たものが知識になるのは、本を読む行為が往々にして「考える」ことを伴うものだからである。何かについて本当に「知る」ということは、少なくとも知識というレベルにまで深まっていなければならない。
「無知の知」を知ることが人間を成長させる
人間にとって一番大事なのは「自分は何も知らない」と自覚することである。「無知の知」を知ることを読書は教えてくれる。本を読めば知識が増え、この世界のことを幾分知ったような気になるが、同時にまだまだ知らないこともたくさんあると気づかせてくれる。何も知らないという自覚は、人を謙虚にする。謙虚であれば、どんなことからでも何かを学ぼうという気持ちになる。それは人を際限なく成長させてくれる。
本は言ってみれば、人間力を磨くための栄養である。草木にとっての水のようなものである。
仕事と読書と人が教養を磨く
教養に、知識の量は絶対条件ではない。教養の条件は「自分が知らないということを知っている」ことと「相手の立場に立って物事を考えられる」ことの2つである。そして、教養を磨くものが仕事と読書と人である。この3つは相互につながっていて、どれか1つが独立してあるというものではない。読書もせず仕事ばかりやっても本当に良い仕事はできないし、人と付き合わず、人を知らずして仕事がうまくできるわけはない。
人には寿命があり、その中でできる仕事は限られている。だから経験できないこともたくさんある。それを埋め合わせたり、人生を豊かにしてくれるのが読書である。