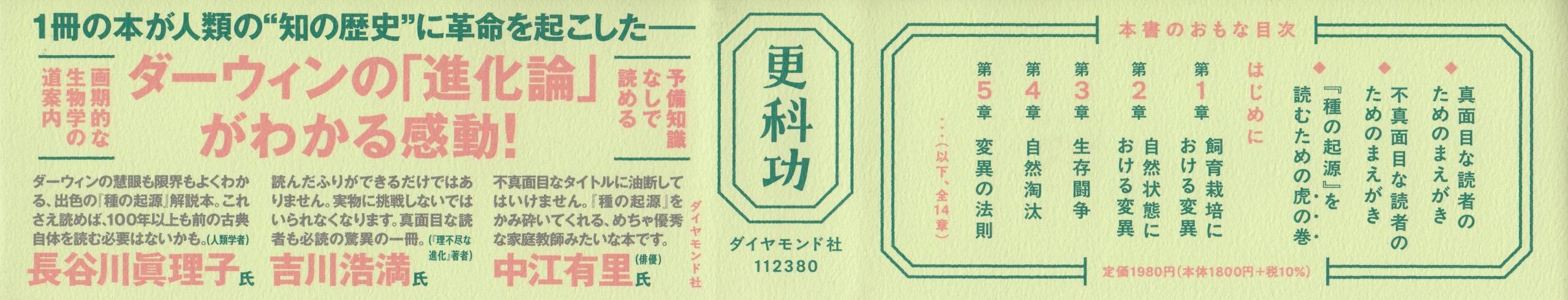『種の起源』が提唱する4つの進化の仕組み
『種の起源』を理解するために最も重要なことは、そこで提唱されている進化の仕組みを理解することである。『種の起源』で提唱されている進化の仕組みは4つ。
①自然淘汰
生存や繁殖に有利な個体が増えていくメカニズム。ダーウィンは自然淘汰の中で、生存ではなく繁殖に有利なメカニズムを「性淘汰」と呼んでいる。厳密に自然淘汰と性淘汰は区別することができないので、性淘汰は自然淘汰の一部と考えた方がよい。
②用不用
よく使用される器官は世代を重ねるごとに発達し、使用されない器官は退化していくというメカニズム。現在では誤りとされている説だが、『種の起源』では進化の仕組みの1つとして採用されている。用不用説は古代から存在する考え方で、当時の進化学者にとっても一般的なものだった。
③生活条件の直接作用
「使用するかしないか」ではなく「環境への順応」によって生物の特徴が変化する説。これも現在では、基本的には誤りとされているが、『種の起源』では進化の仕組みの1つとして採用されている。
④習性
ダーウィンは「習性」という言葉を、基本的には「後天的に獲得された習慣的な行動」という意味で使っているが、同時に進化の仕組みとしても使っている。しかし、これは「生活条件の直接作用」「用不用」の一部であると言える。
『種の起源』最大の発見
『種の起源』の中で一番重要な主張は、自然淘汰を主要な進化の仕組みとしたことである。ダーウィンは、品種改良で使われた選抜の原理を自然界に拡張することで、自然淘汰というものが実際に自然界で働いていることを示す。選抜の原理とは、以下のようなものである。
- 同種の個体の間に変異があり、その中には遺伝するものもある
- 生殖年齢に達するまで生き残る数より多くの子を産む
- 生殖年齢に達するまで、より多く生き残った子が持つ変異がより多く残る
この選抜の原理では、1と2が成り立てば、自動的に3が成り立つ。そこで、ダーウィンは自然界でも1と2が成り立っていることを示し、その結果3が自然界で働いていることを論証した。
莫大な証拠を挙げて、自然淘汰と進化を切っても切れないほどに結びつけ、広範で精緻な観察によって自然淘汰の力の凄まじさを認識した人は、明らかにダーウィンが初めてだった。
ダーウィンの誤り
ダーウィンが『種の起源』で主張したいことは「野生状態の様々な種は自然淘汰による進化で作られた」ことだ。ダーウィンは、まず品種改良について述べてから、その原理が自然界にも適用できることを示して、自然淘汰による進化も事実であることを論証する。
しかし、ダーウィンの考えは、かなり間違っている。その最大の原因は、ダーウィンが遺伝の仕組みを知らなかったことにある。基本的な遺伝の仕組みは、メンデルが解明しており、既に1856年に論文を発表していた。『種の起源』の初版の出版は1859年なので、メンデルの論文発表よりも後だが、発表当時はメンデルの論文はあまり知られていなかったので、ダーウィンは読んでいなかったようだ。
同種の個体の間の違いを「変異」と呼ぶ。ダーウィンは知らなかったが、変異が生じる原因は突然変異であり、変異が維持される原因は遺伝のメカニズムにある。これらは、野生種だろうと家畜や栽培植物だろうと変わらない。しかし、野生種より家畜や栽培植物の方が変異が大きい。これは、野生種には自然淘汰が強く作用し、多くの変異が除かれてしまうからである。にもかかわらず、ダーウィンはその理由を、家畜や栽培植物の方が、環境が多様だからだと考えていた。
ダーウィンは、遺伝する形質を絵の具のようなものだと考えていた。そのため、世代を重ねるごとにどんどん薄まってしまい、最後にはすべての個体は同じ形質になって、変異はなくなってしまうと考えていた。ところが、実際の生物にはいつも変異が存在する。そこで、どこかから無理やり変異を持ってこなければならなかった。そのため、食物の過剰摂取とか、日常的な搾乳とか、実際にはありえない遺伝的変異の供給源を、ダーウィンは想定してしまった。
ダーウィンは、自然淘汰が働いて生物が進化するためには、変異の生じやすさが何よりも重要だと考えていた。そして、変異を生成する原因として「生活条件の直接作用」と「生活条件の変化」「用不用」を考えた。ダーウィンは、実際の進化における遺伝的変異の供給源は、遺伝子などに起きる突然変異であることを知らなかったのである。
現在の知見によれば、既に集団の中には変異がたくさん蓄積されていて、その中から使える変異を選んで活用するのが、自然淘汰である。変異が生じることによって変異が蓄積され、その蓄積された変異を自然淘汰は利用するのだ。したがって、変異の生じやすさは、新種の形成速度に間接的な影響しか与えないことになる。