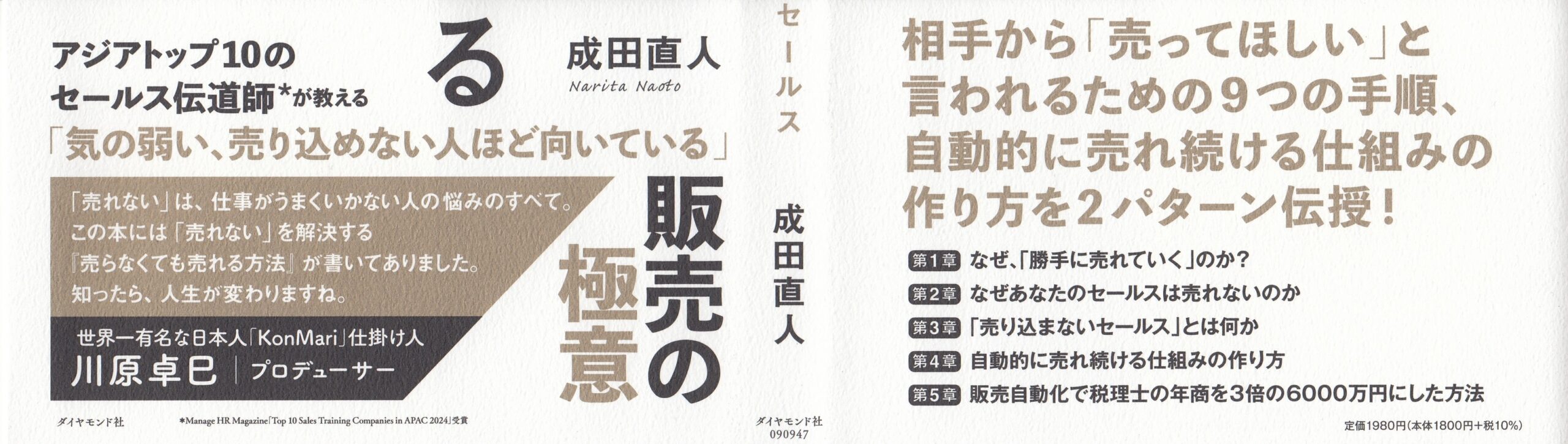「勝手に売れていく」ために必要なこと
人が嫌がる「売り込み」「クロージング」をしても、成果を上げることは難しい。「勝手に売れていく」ための営業手法は、売り込まないセールスである。このセールスを身につけるためには、まずその「セールスマインド」を身につけることが必要である。
- 売れない理由を他人や商品、値段などの環境のせいにせず自責にする
- 一流から学ぶことを通して、自分を比較し、売れない理由を自覚する
- 一流からの学びを1日1個ずつ取り入れ、成功体験を積み重ねる
- 商品知識の勉強をして商品を好きになる
- 他者と差別化する自分の強みを自覚し、さらに自分の強みを伸ばす
- 思考を習慣化できるまで繰り返し実践して身につける
多くのセールスが売れない理由
典型的なダメなセールスには、以下の売れない理由がある。
①お客様の課題に対する仮説がなく、そのための準備もない
お客様の課題認識がないセールスは、顧客不在の売り手起点のセールスである。準備不足で課題認識がないまま一方的な商品説明をすることは、相手の時間を奪っているだけで、お客様は自分と商品やサービスを関連付けて考えない。
②商品と課題が合っていない
取り扱っている商品やサービスが素晴らしくても、それが見込み客の課題に合っていない。この問題を招く要因は4つ。
- 事前準備、リサーチ不足
- 見込み客の課題発掘よりも売り込み重視のセールス設計になっている
- 見込み客の課題が自分ごとになっていない
- 自社商品が顧客のどんな課題解決につながるか理解できていない
③ニーズ確認のための質問が少ない
自社商品やサービスで解決できる問題かどうかを、質問を投げかけながら、現状の課題、見込み客が認識している課題を聞くのがセールスの基本。ニーズ確認の質問の数が少ないのは質が低い人である。その要因は3つ。
- 売らなければならないというセールスマインド
- 商品提案中心のロールプレイングをしている
- 質問リストを用意していない
④商品理解が浅い
自社の商品をよくわかっていないと、お客様に対して「いいと思いますよ」といった曖昧な言い方しかできない。自分の商品を「本当に素晴らしい」と思えるかどうかは商品の知識や理解に尽きる。様々な状況やニーズに応じて、自社商品のどんな点が「刺さる」のかを立体的に考え、その特徴を的確に伝えられるようにしないと売れない。
⑤契約後のフォローアップの質が低い
商品ユーザーやサービスクライアントは、契約後のことを重視する。担当者が伴走してくれ、わからないことをすぐに聞けることが大事である。フォロー体制が構築できていないと、悪い口コミを書かれやすく、リピートや紹介客も生まれない。
「売り込まない」セールス
売り込みをせずとも、相手から「売って欲しい」と言ってもらえる状態をつくるには、以下の手順がある。
①見込み客に対して「どう力になれるか」を考える
まず相手の課題を理解する。その時に、相手の課題を解決するために「どんな手助けができるのか」という視点を持ち、解決策を考える。
②自社・自身の資源を差し出す
今すぐ提供できるサービスだけでなく、課題解決を最優先に置いて、「自社商品だけを売ればいい」という狭い枠を取り払って考える。自社だけでできないことは、他社のリソースを借りられる関係性を構築しておく。
③顧客分析は憑依するレベルで行う
お客様の理解は、表層的なものではなく、とにかく深めていく。お客様と同じ解像度の映像を見ている状態をつくる。とにかく細かく質問を重ねて、お客様に質問をする。
④商談は一発勝負で設計する
事前準備せずに商談には行かない。「これくらいできればいいや」と自分の中で楽をしようと思っている時点で、そのセールスは絶対にうまくいかない。「これで無理だったらしょうがない」ぐらいの作り込みをして臨むことが重要である。
⑤商談中はセールスよりもヒアリング重視
商談中は売り込みや商品説明に時間を割くよりも、どんなことに今困っているのか、どんなことに課題を感じているのかを聞く。
⑥解決策を欲する状態を作る
商談中に潜在ニーズが顕在化されると「なんとかしなきゃ」という優先順位が一気に上がる。質問を通じて、潜在ニーズを引き出すことができれば、「そこを見落としていたな」と話がトントン拍子で進んでいく。
⑦複数の課題解決策を提示「どれがいいの?」と言わせる
1個の解決策だと「予算が合う・合わない」「時期的に難しい」「今すぐできなそう」といった理由が頭をもたげることで、意思決定が揺らぐ可能性がある。3つぐらいの選択肢を提示して、どれがいいかを聞いてみる。
⑧商品提案は最後の最後までしない
商品提案は、最後の最後まで我慢をしてニーズを増大させていくことに徹し、お客様から聞かれるまで、自分から商品提案はしない。
⑨クロージングしない
「どれがいい?」と聞かれた時点で初めて、選択肢を提示するぐらいがいい。