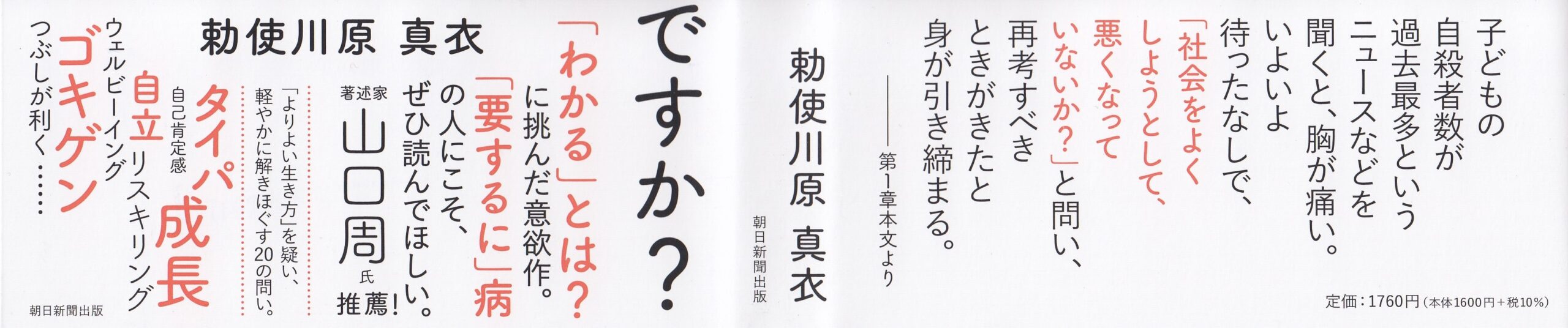わかるとは何か
ChatGPTといった技術革新によって私たちは何となくでも「わかる」という感覚を格段に得やすくなった。いわば「わかる」がファスト化する今こそ、立ち止まり、「わかるとは何か」を考えてみたい。なぜなら、この「分けて」「わかった」気になり、「分け合い(配分)」を決めることが、社会において所与のものかのごとく居座り、ひいては分断を引き起こしていると思えてならないからだ。
「能力」といった納得感の高そうな論理をつくり、個人を振り「分け」、それによってモノやカネを「分け合う」ことは、国や企業など秩序形成に不可欠とされる。
人が人のことを「わかる」ために「分ける」という論理。一説によると「わかる」の語源は「分ける」だとも言う。「分類」することで、その対象の得体の知れなさが軽減され、「分かった(把握できた)」感が生まれる。但し、何でも「分ければ分かる」わけではない。「区分」「分別」のラベル次第では、「分かる」以上の展開も引き寄せる。
「分かる」ために「分けて」いくことは、思いの外「分断」と呼ばれる状態と地続きである。「わかる」とは「分ける」ことと不可分で、どう分けられたかが、分け合いに影響する。私たちはどう分け合って生きるべきか。そのために何を分け、わかる必要があるのか。具体的、実践的な方策は出せていないのが現在地と言わざるを得ない。
「分ける」「わかる」「分け合う」を考えると、平等とは何かや、豊かさ、その前提となる人間観、労働観などにも深く触れていくことになる。「個人」「自立」「競争」「自己責任」「しあわせ」とは何かまで絡む。
「こたえ」を探そうとすると危うい。「正しさ」は文脈依存的だし、誰もが自分は正しいと思って生きている。だから問うべきは「これは正しいのか」ではない。私たちは「問い尽くしているか」を問いかけることだ。
格差とは何か
所得格差、教育格差、格差婚などという言葉まで、「格」と言う言葉は、市民権を得た言葉である。では、格差の「差」とは、「格」の違いなのか。私たちは、「格」のような、そもそも優劣・序列づいた人間観を前提にして「分け」、「わかった」気になっていないか。
「格差」を問題に設定すると、それをひっくり返したかの問題解決策が見えてくる。「格差をなくす」という方針だ。お金がなくて塾に行けないなら無料塾を開く、体験格差が問題なら夏休みの無料イベントを開く。
しかし、その問題は差分を埋めれば、問題解決なのか。「格差をなくす」以前に「格差」とは何かに立ち返りたい。格差と呼んだ瞬間に、経済格差で言えば、お金があった方がいいに決まっていることになるし、体験格差もいろんな体験をさせてあげていることがいいに決まっている。しかし、本当にそうなのか。
「格」とは「地位」「階級」「基準」を示し、ランクづける意が主だが、元々の感じで言うと、木編に「各」と書く。諸説あるが「それぞれ違った枝葉があってこそ、一本のしっかりとした木として立っている」様を模した、という見立てもある。各々の違いというのは、必ずしも上下関係ありきの序列の話ではないということだ。
色んな人がいるよねの「各々」は、いつしか上下垂直方向の序列付けられた存在になり、その前提の上で格差問題が語られている。私たちはこれをそのまま続けるかどうか。
能力とは何か
「学歴偏重」と批判された時代を経て、社会が個人に求める「能力」は変化してきた。「学力」に代表されるような、わかりやすい個人技的な「能力」以外にも、「人間力」「コミュ力」「生きる力」といった、他者との関係性も重視するかのような「能力」の要請が目立って叫ばれるようになった。
範囲も定義も選ぶ側の都合によって変わる「能力」によって、人を分ける。これは、公平性の観点からすると、進化どころか2歩下がっていないだろうか。安易な「わかる」のために、無自覚に人を「分け」、あたかも「分け合い」が公正に行われているようだが、分け合うどころか、分断の正当化が起きていないか。
「よりよい社会」と言うならば、個人に求められる「能力」の要請をはじめとする潮流とはうまく距離をとりたい。能力やそれに伴う競争が仮に批判される向きになれば、言葉尻だけ調整した、なんちゃって「シン能力」が台頭する。